私は、宝塚が好きです。舞台に立つ人たちが好き。その好きという気持ちが、彼女たちにとって応援として届けばいいなと思っている。そして、同時に無数のスパンコールが見せてくれる夢の中にでも、悲しみもある、不安もある、そのことを最近はおかしいと思わなくなりました。未来に向かっていく人の、未来の不確かさをその人と共に見つめたいって思っている。だから、そこにある不安は、痛みは、未来を見ることだって今は思います。好きだからこそある痛みを、好きの未熟さじゃなくて鮮やかさとして書いてみたい。これはそんな連載です。
2階席の奥に座る日は、最初から「今日はあの人を集中して見よう」とかそういうことを決めて2時間35分ほぼずっとオペラグラスを上げる。2階席の奥だと絶対向こうからは見えないという安心があるので臆せずオペラをむけていられるし、人をずっと追いかけて見つめるのって(前回に少し書いたけれど)舞台の見方として王道ではないのかもしれないが、でも観劇体験としてはものすごくど真ん中のことでもあるようにやっぱり私は思うから。芝居は一人一人が一つの作品のために動いて、そして「舞台」としてその場を完成させているけれど、一方で演じる側はみんな一本の時間軸の中で一人一人ずっと、生きている。それを追いかけて、例えば一人の人だけとか、一つの集団だけを見届けようとするとき、そこで見える別の「舞台」を私はとても好きだと思える。誰も物語のためだけに生きているのではなく、人はそれぞれひとつずつ物語を持つ、人生を持つ、舞台だけでなく現実世界だってそう、一人一人の人生の重ね合わせとして世界や舞台があって、そのことが私という一人の人間がオペラや肉眼で「見たい」という気持ちに正直に舞台に向かうとき、よりはっきり感じ取れる気がした。「神の視点」としてではなく、「私の視点」として物語を見るから、あの世界の中に入っていける感覚になる。図々しいけど、でも私がいるからこそ私にしか見えない物語が生まれるんじゃないかな。舞台は作り手にとっては板の上が全てなのだろうけど、見ている側にとってはそんなエゴが深く関わった「観劇体験」こそが受け取る「作品」なのだと思います。
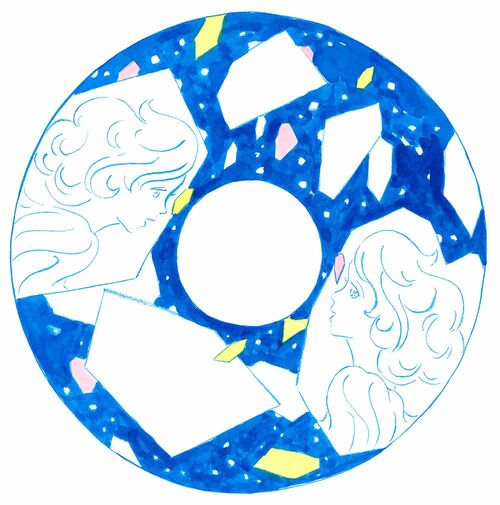
その日もいつものように一人だけをじっとオペラで追いかけて見ようと思った。向こうからは気づかれないだろうし。けれど、私が2階席奥の壁際の席からオペラで見ていた若手の人が、明らかにオペラに気づいたのです。

