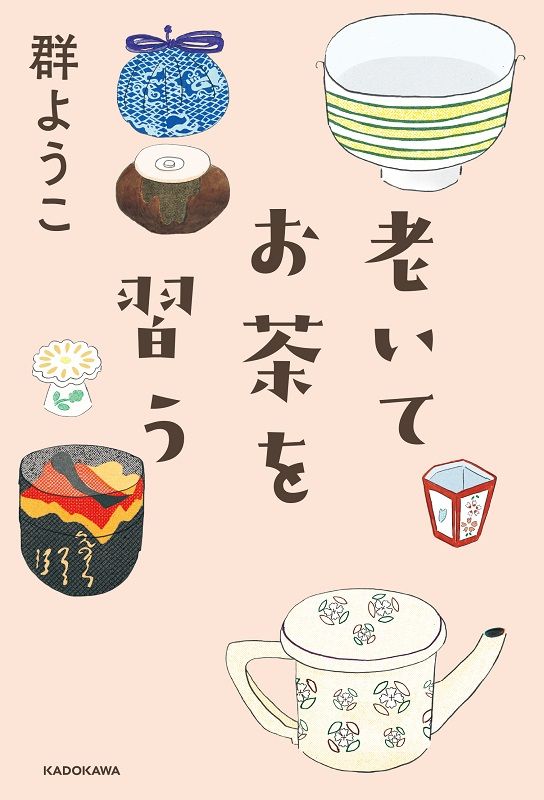数寄屋袋はたまたま30パーセント引きのクーポンを持っていた店で、雨龍間道(あまりゅうかんとう)のものがあったのでそれと、同じ雨龍間道柄のステンレス製の菓子楊枝つきの楊枝入れがあったので購入した。黒文字がいいのかステンレスでもいいのか、師匠に聞いてみよう。これらが揃えば、お稽古に通えるので、早く届かないかなと心待ちにしていた。
こちらも注文して3、4日ですべての品物が届いた。3寸の楊枝はちょっと短かった。楊枝入れについていたステンレス製の菓子切りは、10.5センチの長さだった。3.5寸のものが合うのだけれど、御菓子をいただいた後、黒文字を懐紙にくるんで持ち帰ったとしても、それは次回には使えない。
おまけに黒文字は使う前に十分ほど水に浸けておいたほうが、菓子がくっつかないとあったので、事前の手間もかかりそうだった。
すべて次回、「師匠、兄弟子、姉弟子に聞いてみよう」である。数寄屋袋に必要なものを入れると、形だけは整った。
※本稿は、『老いてお茶を習う』(著:群ようこ/KADOKAWA)の一部を再編集したものです。
『老いてお茶を習う』(著:群ようこ/KADOKAWA)
齢六十八にして、お茶を習うことになった。果てがない稽古が始まった。
齢六十八にして、お茶を習うことになった。事のはじまりは、今から二十年以上遡るのだが、当時、私の担当編集者の女性と、還暦を過ぎたとき、自分たちはどうしているかといった話をしていた。私は、
「いつまで仕事をいただけるかわからないけれど、仕事があればずっと続けていると思いますけどね」
といった。私よりも二歳年上の彼女は、
「私はお茶の先生ができればいいなと考えているのですけれど」
というので、
「そうなったら、私もお弟子になる」
といったのである。(本文より)