
経済成長と密接に関係
「社会保険料を負担する企業の理解を得られなければ、公的年金の制度は持続可能性を失ってしまう。理解を得られるような激変緩和策をセットで提案することが必要だ」=長妻氏
「企業は生産性を上げないと、賃上げはできない。賃上げもできなければ、社会保険料の負担は当然重く感じるだろう。最後は、経済をどう伸ばすのかという問題になる」=加谷氏
伊藤社会保障制度の維持と日本経済の成長戦略は密接に関係しているというところまで、議論は及びました。パート労働者が厚生年金に加入するようになれば、事業者は保険料の半分を納めなければなりません。厚労省は、事業者が半分よりも多く負担できる案も検討しています。加谷さんは「事業者は負担が増えて嫌かもしれないが、発想の転換が必要ではないか」と指摘されました。社会保険完備の企業で働きたいと希望する人は多いですし、人手不足の中で良い人材に来てもらうためには、働きたいと思える労働環境を整えなければなりません。従業員の社会保険を充実させることは、企業が生き残るためでもあるわけです。
そのためには、企業は生産性を高めて、賃金を上げられる、加えて社会保険料の負担に耐えうるだけの体力をつける必要があります。それができない企業は退場を迫られます。それで良しとするかどうかは議論の分かれるところだと思いますが、加谷さんは「企業を淘汰する効果はあり、経済成長にもつながる」と言われました。社会保障と経済成長の関係や、改革を進める時の激変緩和策の設計を含めて、国会で広く深く議論するべきです。
吉田社会保障制度は複雑です。国会の論戦でも、所得税のかかる「103万円の壁」と、社会保険料のかかる「106万円の壁」を混同している議員がいました。国民が安心できる年金制度に改革することは待ったなしの課題です。パート労働者も厚生年金の保険料を払うことになれば、今の手取りは減ってしまいます。嫌だと思うかもしれませんが、将来の年金は増えるわけです。時間軸の視点を忘れずに、きちんとしたデータを示しながら、国民に納得してもらうことが大切です。老後の暮らしを想像する時に参考になる具体的な数字で説明してほしい。

第3号被保険者の制度は、共働きやひとり親の世帯が増える中、不公平感を抱く人が多くなっています。右肩上がりの時代を前提にしたモデルは、もはや成り立たなくなっています。老後を年金で悠々自適に過ごすことも、なかなか難しくなっています。厳しい現実ですが、年金制度の見直しは、一人ひとりが働く意味を問い直したり、人生の設計を考え直したりするきっかけになるかもしれません。意欲のあるうちは働こうと思うなら、健康でなければなりません。制度を支える側に回る人が様々な形で増えていけば、社会を維持することにつながります。
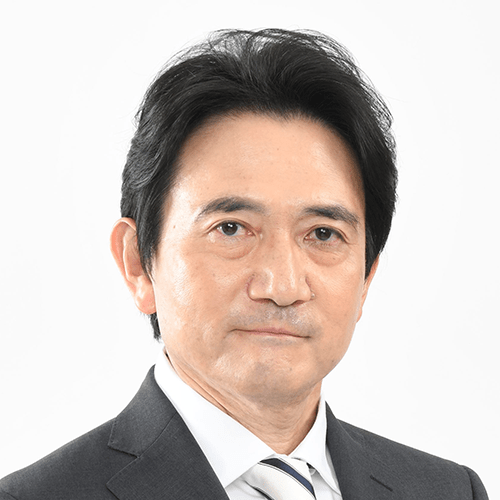
伊藤俊行/いとう・としゆき
読売新聞編集委員
1964年生まれ。東京都出身。早稲田大学第一文学部卒業。1988 年読売新聞社入社。ワシントン特派員、国際部長、政治部長などを経て現職。
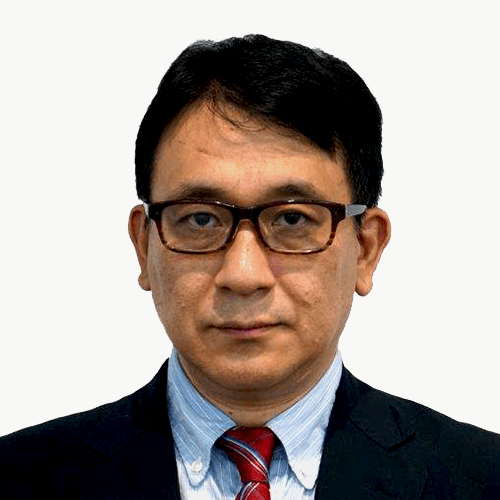
吉田清久/よしだ・きよひさ
読売新聞編集委員
1961年生まれ。石川県出身。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。1987年読売新聞社入社。東北総局、政治部次長、 医療部長などを経て現職。
