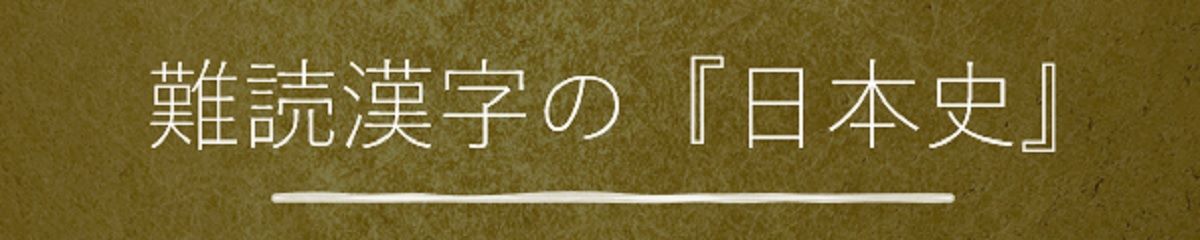正解は…
正解は「ずりょう」でした。
ーーーーーー
受領(ずりょう)とは、国司四等官の筆頭者で(原則は国守)、令制国に赴任して行政責任を負う者を指す。
国司四等官は元来、共同責任を負ったが、平安時代の変革により筆頭者が責任・権限を負うこととなり、職名が受領と呼ばれることとなった。おおよそ四位、五位どまりの下級貴族である諸大夫がこの任に当てられた。
令制国に着任した国司が前任者から引継手続きを受けることを「受領(する)」と言い、それが職名になった(なお、後任者に文書や事務の引継を行うことを「分付(する)」と称した)
ーーーーーー
皆さんは正確に読めましたか? では次回もお楽しみに。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%97%E9%A0%98)最終更新 2024年5月11日 (土) 14:25