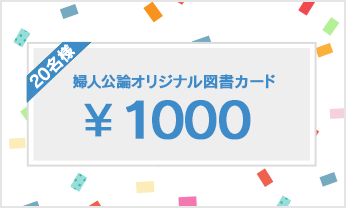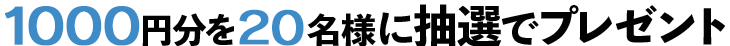AIにない人間の強みとは
竹内大学では、どのような授業をなさっているのですか?
菊池大学院時代からの専門である「キャリア形成論」がテーマです。まず、ライフキャリアという視点から自分の人生をデザインし、それを踏まえてワークキャリアを磨くために、学生時代に何をすべきかを考えてもらいます。大事なのは、時代の変化に対応できる能力を身につけること。毎回、「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」や「社会の多様性」などの課題を設定して、講義を行っています。その中で、最近避けて通れないと感じるのがAIですね。
竹内やはりそうですか。実は9年前のこの対談で、私は「やがてAIを搭載したロボットと一緒に働く時代が来る」と話していました。実際に、世の中はその通りになってきましたね。私の仕事で言えば、専門の方に頼んでいた翻訳作業がかなり自動化されました。でもそれは、扱うのが文字通りに訳せばいい科学書だから可能だとも言えます。一方で、小説の翻訳となると意味が通じなくなったりします。AIには心や意識がないので、意訳が難しいんですね。
菊池そうですね。何かを創造していくのは、引き続き「人間の仕事」なのかな、と思います。竹内さんは教育とAIの関係をどのように考えていらっしゃいますか?
竹内私は16年に、小中学生などを対象とした「YESインターナショナルスクール」を開校しましたが、根底には、子どもたちにAIに負けない「生きる力」を身につけてほしい、という思いがありました。AIで代替可能な暗記型スキルではなく、自ら発想する思考力を養うことが重要です。何かをゼロから作ることは人間にしかできないし、これからはAIを使いながらいかにクリエイティブな仕事をするかが大事だと思います。
菊池どうやってそういう力を身につけるのでしょう?
竹内キーワードは「遊び」です。小学生のうちは思い切り遊ぶのがいい、というのが私の持論で、それを通して想像力や理解力が鍛えられていくはず。プログラミングの学習にしても、教科書通りの課題ではなく、遊びの中なら、楽しく取り組めるじゃないですか。
菊池「生きる力」も「遊び」もすべて人間の心につながっていますよね。私は昔から、芸能活動も教育も、届ける先は人の「心」であって、そこに届けられなければ価値は生まれないと感じていました。ですから大学院修了後、通信教育で心理学を学んだのです。
竹内それもまた素晴らしいです。
菊池お話をうかがって、AIの時代だからこそ、心や感覚というものについて、もう一度考えてみようという気持ちになりました。