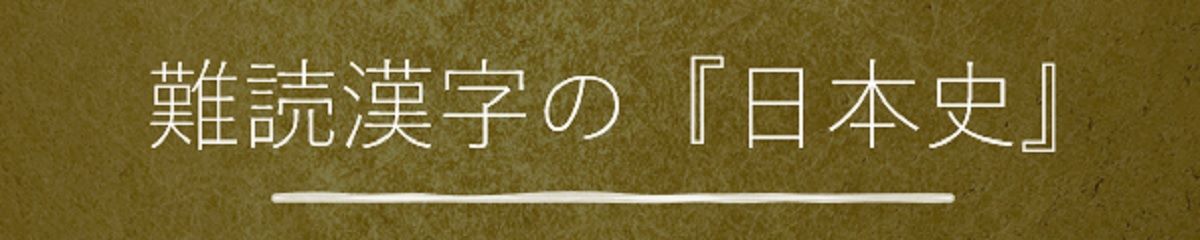正解は…
正解は「せんじ」でした。
ーーーーーー
天皇の命令・意向(勅旨)が太政官において太政官符・太政官牒などとして文書化される際、文書作成を行う弁官局の史が口頭で命令・意向を受ける。このとき、弁官史は、命令・意向の内容を忘れないために自らのメモを作成した。このメモが、当事者へ発給されるようになり、文書として様式化していき宣旨となった。
文書には、弁官・史などの署名しか記されなかったが、天皇の意を反映した文書として認識され、取り扱われた。印璽なき文章に権威が付加されることになり、幕末にはしばしば偽勅が発せられることになった。
ーーーーーー
皆さんは正確に読めましたか? では次回もお楽しみに。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%A3%E6%97%A8)2025年5月28日 (水) 21:14