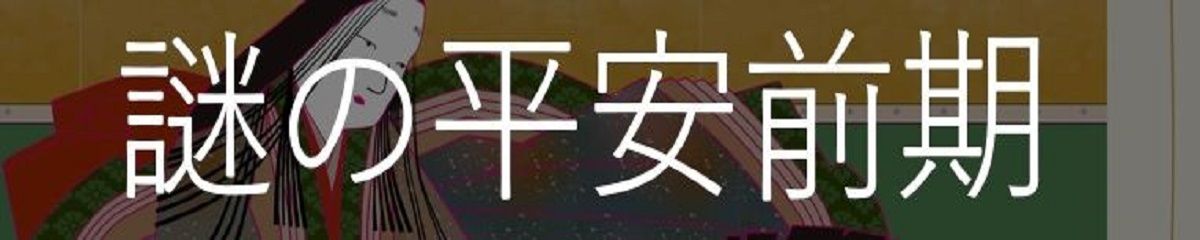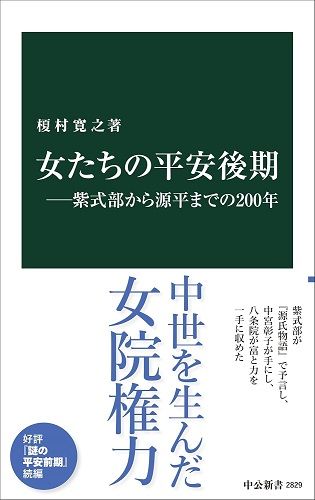道長引退後の倫子
倫子は道長が出家したのちも長暦3年(1039)まで出家しなかったようで、道長が安心して出家できるバックアップになっていた。
『大鏡』は、道長全盛時代に唯一源氏でありながら彼女が「幸ひ」人だったといい、『栄花物語』は、倫子の存在があってこそ道長の栄花が達成できたとする。
しかし彼女が、道長が引退したのちも摂関家の中心でいつづけたことはあまり注目されていないようだ。
道長没後も彰子がその権威と権力を行使できたのは、道長と同等以上の権威を持つこの母が現役だったことが大きいだろう。
それは、摂関家の女性集団における彰子のポジションとも関係してくる。
※本稿は、『女たちの平安後期―紫式部から源平までの200年』(中公新書)の一部を再編集したものです。
『女たちの平安後期―紫式部から源平までの200年』(著:榎村寛之/中公新書)
平安後期、天皇を超える絶対権力者として上皇が院制をしいた。また、院を支える中級貴族、源氏や平家などの軍事貴族、乳母たちも権力を持ちはじめ、権力の乱立が起こった。そして、院に権力を分けられた巨大な存在の女院が誕生する。彼女たちの莫大な財産は源平合戦の混乱のきっかけを作り、ついに武士の世へと時代が移って行く。紫式部が『源氏物語』の中で予言し、中宮彰子が行き着いた女院権力とは? 「女人入眼の日本国(政治の決定権は女にある)」とまで言わしめた、優雅でたくましい女性たちの謎が、いま明かされる。