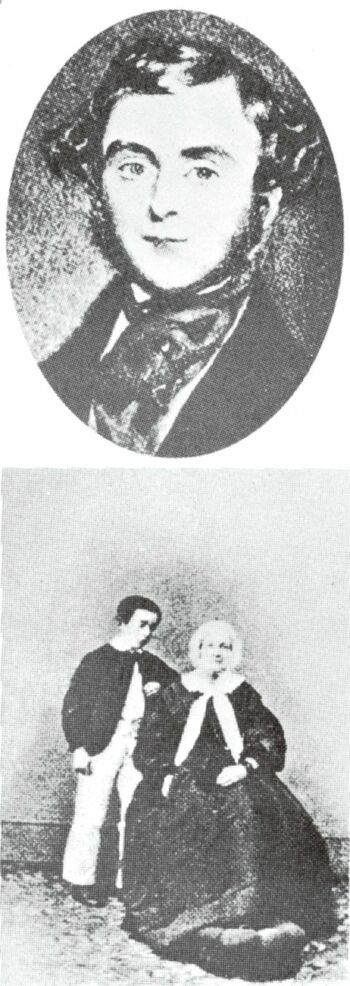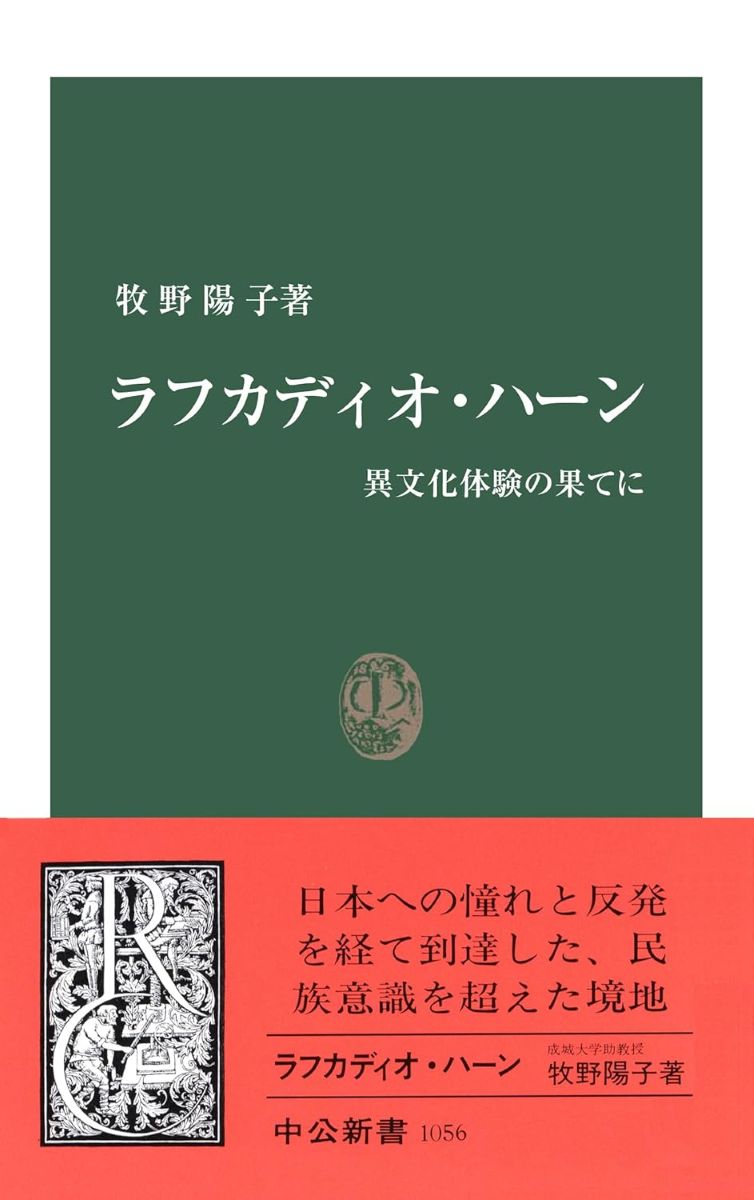ロンドンのスラム街をさまよい…
大叔母は黒ずくめの服に身を固め、ヴィクトリア朝の倫理道徳を体現したような厳格な人だった。
ハーンはその人に愛情を感じることはなく、部屋に掛かっているイコンの聖母子像をみつめては、ひたすら懐かしい母への思慕の情を募らせていた。
十三歳になるとハーンはイギリス中部、ダラム近郊のカトリック系の寄宿学校、聖カスバート・アショー校に入り、一時期、パリ近郊の神学校にも送られている。
こうして大叔母は一貫して思春期のハーンに厳しい宗教教育を課したが、一方でハーンがその多大な財産を相続できるようにもしていた。
ところが、そこへヘンリー・モリヌークスなる遠縁の者が現れて、大叔母に巧みに取り入りはじめる。
大叔母は思うように神学を修めないハーンを疎んじるようになり、モリヌークスに言われるまま資産を託す。ハーンは休暇になっても家に帰れなくなる。
不運は重なり、ハーンが左目を失明してまもなく、父チャールズがインドから帰国途中マラリアで死亡した。翌年にはモリヌークスの事業失敗のために大叔母も破産してしまう。
ハーンは退学させられ、その後の一年半は生涯で空白になっている。ひとりロンドンのスラム街をさまよって都会の裏側の悲惨さをいやというほど味わったらしい。
そして縁者を頼りに、一人アメリカへの移民船に乗り込んだ。
※本稿は、『ラフカディオ・ハーン 異文化体験の果てに』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。
『ラフカディオ・ハーン 異文化体験の果てに』(著:牧野陽子/中央公論新社)
他のお雇い外国人と異なり、帰るべき故郷を持たないラフカディオ・ハーン。
ハーンが神戸、東京と移り住むうちに、日本批判へ転ずることなく、次第に国家・民族意識を超越し、垣根のない文化の本質を目ざしてゆく様子を描く。