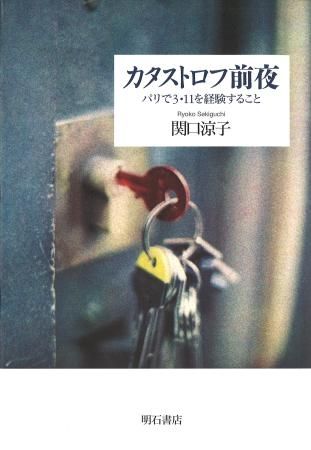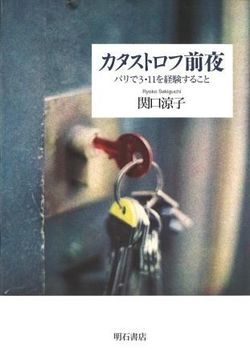
このささやかな日常は、厄災の前あるいは後にある
東日本大震災の発生から9年の日に合わせて刊行された本を、まさかこんなカタストロフへの予感のなかで読むことになるとは思わなかった。本書はパリ在住の詩人・翻訳家がフランス語で書いた3冊の本を自ら訳し、一つにまとめたものだ。したがって各章は独立した著作であると同時に、ゆるやかに繫がりあっている。
「これは偶然ではない」と題された章は、被災地から遠く離れた地で記された3・11直後の日録だ。そこでは阪神・淡路大震災など過去のカタストロフの記憶や、自らの詩の題材にしたことがある異国での厄災が想起される。それらをあえて震災「前夜」のエピソードから書き起こすのは、私たちのささやかな日常はつねに「カタストロフ」の前あるいは後にある、という認識に著者が立つからだ。
続く「声は現れる」の章は身近な2人の人物の死をモチーフとした断章形式の散文詩。留守電やラジオの録音に残された声の記憶が、その不在ゆえにいっそう生々しく立ち上がる。最後の「亡霊食─はかない食べ物についての実践的マニュアル」は食を題材とした軽妙なエッセイで、鋭い文明批評がきわだつ。
この3作を繫ぐのは「亡霊」というモチーフだ。それは愛おしい人物の「声の記憶」を象徴するものでもあり、真の名で呼ぶことが忌まわしいもの、すなわち放射能の言い換えでもある。その両義性に軽いひっかかりを感じたが、謎はすぐ解けた。もとの本の刊行は「亡霊食」「声は現れる」の順。ならば「亡霊」のもつ意味は時を経ることで深められていったのだ。
「コロナ後」の不安定な世界では、「亡霊」に対する両義性はいっそう普遍性をもつのではないか。
著◎関口涼子
明石書店 2400円