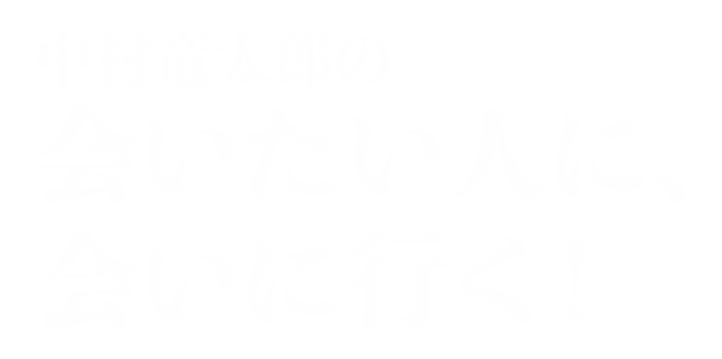堀 父がバンドマンだったと知ったのは私が小学校に入学してからですね。ギターがやけに上手いなあと感心していたら、ギタリストだった(笑)。当時、ホリプロは赤坂見附の裏通りに薄暗くて狭い事務所を構えていました。議員宿舎まで人力車が連なっていて、料亭前には芸者さんがいて、お大尽みたいな酔客が百円札をばらまいていて。そんな光景が日常的にありました。
中村 へえ、赤坂に人力車が走っていたんですか!
堀 自宅は赤坂の繁華街のど真ん中。裏は東洋一のキャバレー「ミカド」、こっちは力道山が刺された「ニューラテンクォーター」、その先は米軍宿舎。おっかないわけです。そんな猥雑な環境だから、親からは夕方6時以降は外出するなと言われていました。
中村 家業が芸能プロダクションだということはいつ知ったのですか。
堀 小学校2、3年生だと思います。それまでも、テレビで見かける芸能人が家によく来るなあとは思っていたけれど、それが当たり前だったし、私は「父はサラリーマンだ」と思い込んでいましたから。赤坂にいた頃は鈴木ヒロミツが僕のベビーベッドをうちに運んでくれたそうです。しょっちゅう出入りしていた和田アキ子には「ゴリラ!」なんて言って、「クソガキ!」って叱られていましたね。生意気なガキでした。
中村 怖いもの知らずというか。(笑)
堀 小学校の同級生には典型的な良家の子もいたので、僕のことを、あの家の子とは付き合うな、なんて言う人もいました。同級生の誕生日会によばれていたのに、前日になって「お母さんがよんじゃだめだって」というのが2~3回。もちろんそいつらのことはぶん殴りました(笑)。結構やんちゃでしたね。
中村 当時は芸能=得体の知れない社会、という偏見があったのでは。
堀 いまは本当に健全化したというか、当時と比べると夢のようです。
中村 子ども時代は何になりたかったんですか。
堀 コメディアンです。映画の「社長」シリーズが大好きで、三木のり平さんやフランキー堺さんとか。それにフーテンの寅さん。コメディが好きだったんです。たしか5、6歳のとき、父が「欽ちゃん(萩本欽一)に会いに行くけど、お前も行くか?」って言うので、ついて行きました。渋谷パンテオンの横にあったフランセという喫茶店。父は欽ちゃんと話している。
記憶にはないんですけど、私は横でなにかモノマネとかやっていたそうで、そしたら欽ちゃんが「君はいいコメディアンになるよ」と言ってくれて。それをずーっと信じていたんですよ(笑)。それで16歳のとき、『欽ドン!良い子悪い子普通の子』でふつ夫役の長江健次が降板したので、ふつ夫のオーディションを受けると父に話したら、烈火のごとく怒って反対されました。
中村 面白い(笑)。お父様はなんておっしゃったんですか?
堀 「お前、タレントになんかなったら、身ぐるみ剥がされて生きていけなくなるぞ。なんにもできなくなるぞ」と。あんまり怒るものだから断念しました。
中村 お父様の言葉は当時の芸能界を物語っているようで、迫力ありますね(笑)。小さい頃はホリプロを継ごうという気持ちはありましたか。
堀 まったくないです。ただ高校時代に裏方に目覚めました。高2のときの学園祭で実行委員長をやりたかったんですけど、停学経験があったのでできなくて。代わりに傀儡を立ててね。
中村 傀儡ですか。(笑)
堀 生徒会長と、実行委員と。そういう子がいないと予算がおりない。僕は屋外のイベントを仕切る担当になるんですけど、そこでもう鬱憤を晴らすようにやりましたね。自分もステージに出てましたから。先生を生徒役にして、僕が先生役をやるんですが、先生のモノマネがウケて、もう、それからえらいモテるようになっちゃって。
そのときは芸能界に行こうとか、裏方になろうとかは思っていなかったんですけど、学園祭を大成功させて、自分が前に出なくても人を笑わせることはできるなと思ったんです。
中村 プロデューサーの才能が開花したんですかね。
堀 当時から物怖じしない性格で、父親に連れられて業界のパーティによく顔を出していたんです。あるとき見るからに大物のオーラを漂わせている御仁がいたんです。
中村 それは……?
堀 現在の芸能界を作ったといわれる渡辺プロダクションの渡辺晋社長です。誰も彼に近寄らなくて、社長のまわりにドーナツ型の空洞ができてるから、挨拶に行った。そしたら「将来君はどうするの?」「いや、なにも考えてないですね」「ダメだよ、お父さんの跡を継がないと。お父さんがこれだけやってきたことが無駄になるじゃないか」。その言葉があとになって、ズシンと響いてくるんです。