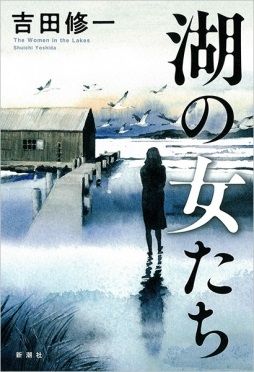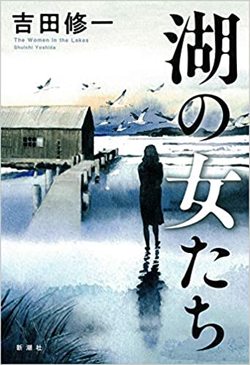
小説とはかくも人を畏怖させるものなのか
読み終わった後、(なにか凄いものを読んでしまった)としばし茫然とした。人間の憎悪の連鎖とは、かくも不可解でおぞましいものなのか──と。
最初に登場するのは、琵琶湖近くの介護療養施設「もみじ園」で働く介護士の豊田佳代。ある日、入居者で百歳になる男が亡くなった。人工呼吸器の不具合による事故死か医療ミスか。西湖署の刑事たちが捜査にやってくる。
雨の日、刑事の濱中圭介は追突事故に遭う。後車を運転していたのは、自分が取り調べをした佳代だった。このとき2人は、互いの奥底に潜む性的嗜好の闇を一瞬にして見抜き強烈に惹かれあう。一方、記者の池田立哉(たつや) は、過去の薬害事件の真相を追ううちに、亡くなった百歳の男の一枚の写真を偶然に見つける。そして、男の過去に導かれ、旧満州・ハルビンにたどりつく。
この男女3人は「百歳の男の死」「歪んだ欲望」「封印した過去」に囚われ、のめり込んでいくのだ。まるで腐臭を漂わす夏の湖に呑み込まれたように。その過程が、リアルかつ冷徹な筆致で描かれる。違法な取り調べで犯人をでっちあげようとする先輩刑事や、過去の悲惨なニュース記事をシェアしあう少年少女グループなど、登場人物たちみんな、閉塞感の中で絶望しきっているようだ。足元深く沈むしか行き場がないように。
湖の底に堆積しているのは、この国がタブーとしてきた歴史や犯罪の闇、人々の悪意と欲望の連鎖の汚泥だろう。著者は、インモラルな関係を続ける男女、さらに自ら深みに堕ちていく佳代を最後に引き上げ、その汚泥を吐き出させている。事件の真相が明らかになる夜明け、湖面に光射すシーンに感じるかすかな再生。そのぞっとするような美しさに、小説とはかくも人を畏怖させるものなのか、とただ慄然とするばかりだった。