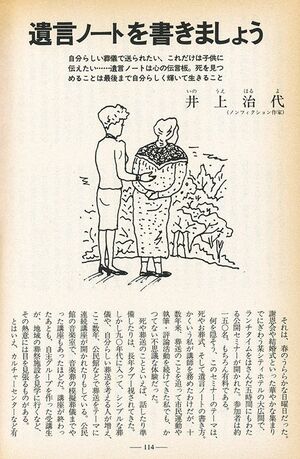年賀状欠礼の挨拶状に
いくら「理想の最期」を思い描いても、死後の手続きを自分で行うことはできません。家族または業者に託す必要が出てきます。前出の井上さんも記事の中でこう述べていました。
「『好きなようにして』と遺族にゲタを預けるより、『これがいい』と言い残してあげたほうが、ずっと『遺された者のため』であり、『思いやり』があると言えそうだ。そして遺族は『本人の希望通りにしてあげられた』という充足感が湧いてくる」と。
最後に、井上さんが記事内で紹介した事例をご紹介します。その女性は姉を亡くした年の年賀状欠礼の挨拶状に、次のように書いたそうです。
「本年3月、82歳の姉Aが死去しましたので、新年のご挨拶をご遠慮申し上げます。私もボチボチ考えておく必要ありと思い、自分の葬儀に関し遺言いたしました。
1.香典は辞退
2.坊主、神主、牧師の世話になるべからず
3.通夜不要
4.最後のお別れという儀式はやるな(責任の持てない死後の顔なんか見られたくない)
5.可能な限り簡素にやれ
以上でございますので、その節はご協力願い申し上げます。それでは、良いお年をお迎えくださいますようお祈り申し上げます」
実にあっぱれです。
次回は「お墓、どうしてますか?」のアンケート回答をご紹介します