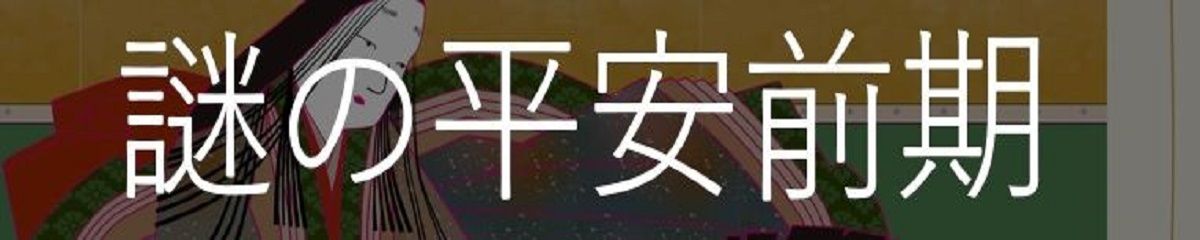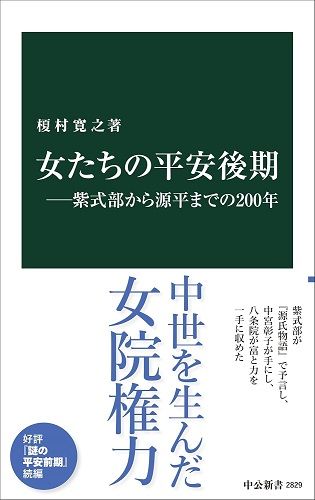道長の目
妍子は派手好みの性格で、終始地味を好んだ彰子とは違う。
環境や性格から見ても、少なくとも姉のために粉骨砕身するとは思えない。
彼女らが常に気にしていたのは、お互いではなく、父親としてではない、冷徹な政治家としての道長の目であろう。
※本稿は、『女たちの平安後期―紫式部から源平までの200年』(中公新書)の一部を再編集したものです。
『女たちの平安後期―紫式部から源平までの200年』(著:榎村寛之/中公新書)
平安後期、天皇を超える絶対権力者として上皇が院制をしいた。また、院を支える中級貴族、源氏や平家などの軍事貴族、乳母たちも権力を持ちはじめ、権力の乱立が起こった。そして、院に権力を分けられた巨大な存在の女院が誕生する。彼女たちの莫大な財産は源平合戦の混乱のきっかけを作り、ついに武士の世へと時代が移って行く。紫式部が『源氏物語』の中で予言し、中宮彰子が行き着いた女院権力とは? 「女人入眼の日本国(政治の決定権は女にある)」とまで言わしめた、優雅でたくましい女性たちの謎が、いま明かされる。