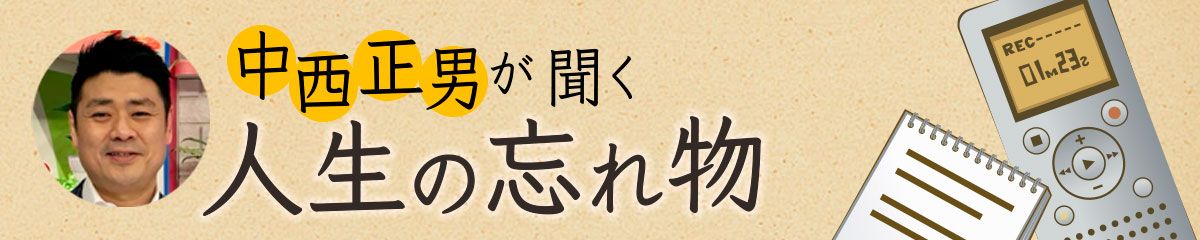浪曲になじみのある人は本当に少ない
私の小さい頃でも、すでに浪曲と言えば銭湯で年寄りがうなっているというくらいのもので「なんかよく分からんけど、年寄りが好きなもんなんやな」という意識でした。そこから何十年も経ってるわけですから、当時若いあんちゃんだった私らがもう70歳、80歳になっているわけです。風呂屋でうなっていたおじいさんはとっくにいなくなってしまっている。となると、リアルに浪曲が好きで、浪曲になじみのある人は本当に少ない。それが現状だというのは強く噛みしめています。
また、単に馴染みがないということだけでなく、今の社会における人の心のカタチみたいな変化も浪曲を遠ざける大きな要素だと思っています。
なぜ昔は浪曲が流行っていたのか。人と人との結びつきが強くて、近所で食べ物の貸し借りをしたり、しょう油を借りたらかぼちゃの煮物もつけてお返しをしたりするとか、そういう関係が当たり前のようにありました。しかも戦争もあって、みんなが本当に大変な中で暮らしていた。人の情がなければ成立しないほどみんなが貧しかった。義理人情、親孝行といったものが普遍的に詰まっていたと思うんですが、今はそういうものが薄くなりました。
受け手の側に「これはグッとくる話だ」という感覚がないと、これはね、もう本当にどうしようもないんです。いくら義理人情の詰まった話をしたところで「で、それがどうしたんですか」と言われると、もうその先がない。終わりなんです。
9代目横綱・秀の山雷五郎を描いた「情け相撲」という話がありまして、崖っぷちの相撲取りのお母さんから息子に勝ち星を譲ってやってほしいと秀の山が頼まれるんです。迷いながらも秀の山は土俵に上がるんですけど、実際に取り組みが始まるとやっぱり真剣勝負の血が騒いで本気で倒しにかかる。厳しいのど輪攻めをした時に、パッと顔を見ると、苦しんでいる相手の力士の顔がそのお母さんにそっくりだった。その瞬間、力が抜けて負けるんです。
あくまでも本気で勝とうとしたが一瞬の情が出てしまう。ここの味が一番のポイントでもあるんですけど、多くの今の若い人からすると「八百長」という一言で終わってしまう。この感覚の違いというか、それがある中でどう浪曲を楽しんでもらうのか。ここはすごく難しい話だと感じています。