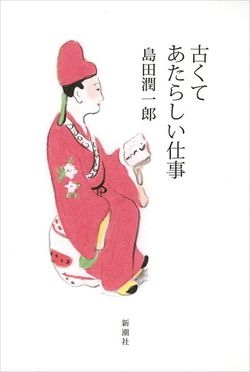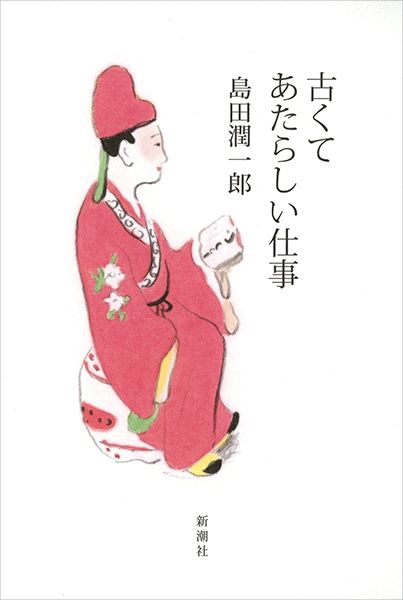「だれかのために」という思いが原動力
2009年に、夏葉(なつは)社という出版社を立ち上げました。社員は僕ひとり。文芸書を中心に、1年に3、4冊の本を企画・編集する。作った本を発送する。本を置いてくれそうな全国の書店を回って営業する──。この10年間すべてひとりでやってきて、考えたこと、あらためて感じた本の豊かさ、「いい仕事をしたいよね」という思いを書いたのがこの本『古くてあたらしい仕事』です。
出版社を始めたというと「すごいですね」と言われますが、それは誤解です。31歳で転職活動をした時は、50社連続で不採用になりました。そんななか、仲の良かった従兄が事故で急逝。混乱し、転職活動もままならなくなった僕が、あたらしい「仕事」として決めたのは「息子を亡くした叔父と叔母の心を支えること」でした。一編の詩を本に仕立て、彼らにプレゼントしたい。それが出版社を始めたきっかけです。
でも10年経って、力をもらったのは僕のほうだったとわかりました。亡き従兄の存在にも励まされ続けています。いま僕は、この仕事を1年でも長く続けたいと思っていて、そのためにどうすればいいか、日頃から考えています。
理想は、子どものころから通っていた中華料理屋さんの仕事ぶり。コツコツ誠実に。自分を大きく見せない。目の前のお客さんを信じて一冊の本を作る。出版というと頭脳労働のように思われがちですが、肉体労働のように汗をかき、嘘のない仕事をしたいなと思います。
5年前に子どもが生まれたことも、仕事に対する考え方に影響を及ぼしました。長男は、同じ年頃の子たちと比べると、言葉や動作がゆっくりしています。気がやさしく、鬼ごっこをすれば鬼ばかり。でも、そんな彼のような人たちの個性が尊重される社会であってほしい。
本や音楽などあらゆる芸術はそういう人たちのためにあるし、僕も出版社として声になりにくいものを声にし、売れ線ではない本を果敢に作り続けたい。それが、ある読者にとっては救いになるかもしれないし、大手ではなく、ひとりでやっているからこそできることでもあります。
なんて格好いいことを言いつつ、初心を忘れることも。気のゆるみが透けて見えるのか、2年に一度くらい、誰かにものすごく怒られます(笑)。そんな時に思い返すのは、これまで仕事をご一緒した方々のこと。とくに本書の中でも触れた、今は亡き和田誠さん、最初に出した本に巻末エッセイを書いてくださった荒川洋治先生らのことを思うと、背筋が伸びる気持ちになります。
本書を執筆してみて、あらためて感じたのは、僕の仕事の原動力は「だれかのために」という気持ちだということ。「こんな本を作ったら、あの人が喜ぶんじゃないか」とひとりの顔を思い浮かべて本を作る。すると、別の方も「私も好きです」と喜んでくれる。その感想がモチベーションになります。
叔父と叔母のために作った『さよならのあとで』という詩集も、娘さんを亡くしたお母さんが同級生に贈るためにと200冊注文してくださったことがありました。今後もし会社が潰れても、「だれかの役に立った」という手ごたえは一生残るでしょう。
仕事って、必ずしもお金が発生することばかりではないですよね。たとえば介護でも家事でも、「だれかのために」と思えることがあれば、それも立派な仕事。そんな心の支えを見つけることが、生きるということだと思います。