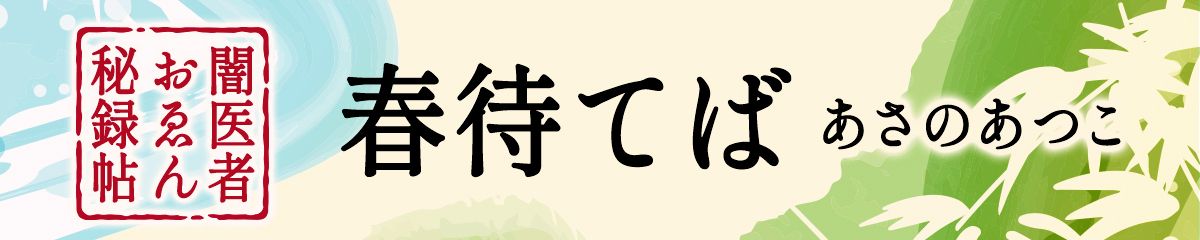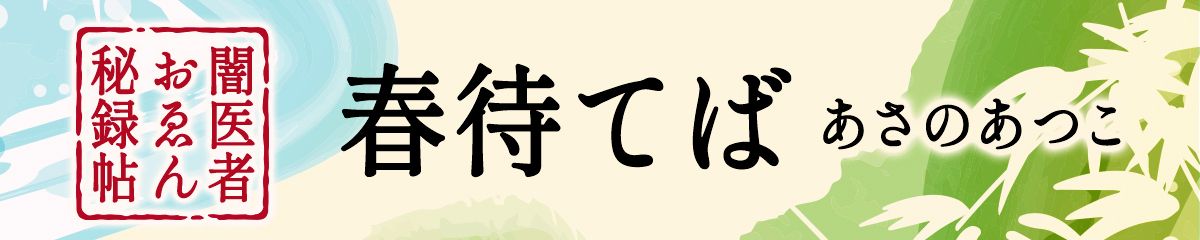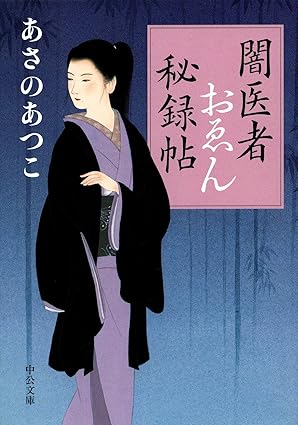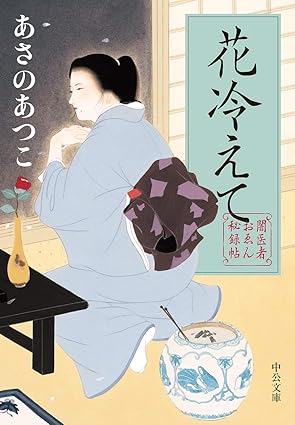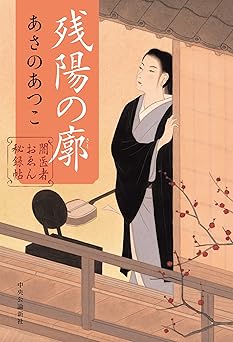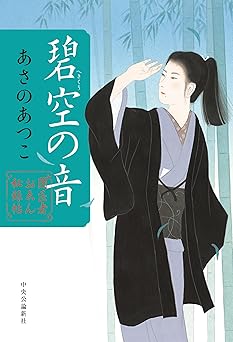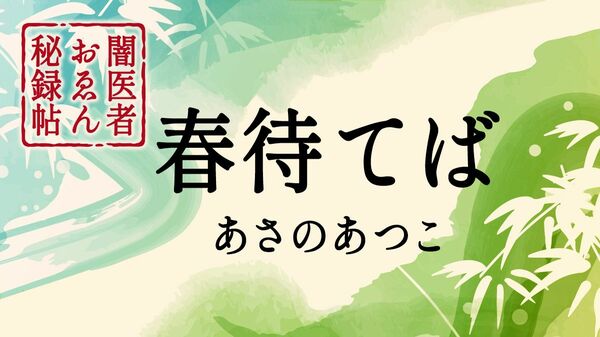
一
嵐が来ます。
末音(すえね)が告げた。ならば、嵐が来る。間違いなく。
おゑんは薬研車(やげんぐるま)の軸から手を離し、立ち上がる。
廊下に出る。空を見上げる。
晴れていた。
濃い青色の空を雲が流れている。雲は青が透けて見えるほど薄く、布に広がった染みのように歪(いびつ)だ。まだ、冬を纏った風が吹き付けて、身体から熱を奪っていく。それでも、光そのものは温かい。手のひらをかざせば、温(ぬく)もりを掴める気がする。
おゑんは光にかざした指をゆっくりと握り込んだ。
「嵐が来るってのは、いつぐらいになるんだい」
振り返り、調合台の前に座る末音に問いかける。白髪を茶筅(ちゃせん)に結った老女は匙を置き、小首を傾げた。そういう仕草が、皺の目立つ末音の顔を不意に若返らせる。むろん、一瞬だが。ただ、おゑんも末音が幾つなのか、よくわかっていない。物心ついたときには、既に傍らにいたし、幼いころの記憶を辿ってみても、老女の姿しか思い浮かばない。
もっとも、年齢など、さほど肝要でないし、知る意味もないと、こちらは、よくわかっている。おゑん自身、自分の歳を気に留めた覚えは、ほとんどなかった。
人は誰も歳を重ねて生きていく。今日よりも明日、今年よりも来年、老いていく。それは、咲いた花が散り、実が熟すのと同じように、東から昇った日輪が西の端に沈んでいくのと同じように、この世の揺るがぬ理(ことわり)だ。
抗うつもりは毛頭ない。
ただ、まだ少しばかり、生きてはいたかった。この身が老いて、現(うつつ)の生に耐え切れなくなるまで、そこそこの、いや、かなりの年月が欲しい。
やりたいことも、やらねばならぬことも堆(うずたか)く積み上がっている。
「そうですの。夜半にはなりますかの」
末音が吹き込んできた風に眉を顰めた。
「おゑんさま、戸を閉めてくだされませ」
「あ、そうだね、ごめんよ」
慌てて、障子戸を閉める。おゑんと末音は、調合部屋にいた。文字通り、さまざまな生薬(きぐすり)をここで調薬する。粉薬も多くあるから、風は大敵だった。粉を散らすし、埃を運んでも来る。風を阻むため、戸も窓の障子も二重にしてある。なのに、ついうっかり、開け放したままにしてしまった。
「勘弁だよ、末音。あたしとしたことが、ぼんやりしてたね」
「ほんに、おゑんさまらしゅうもございませんな」
深い緑色の粉薬を玻璃(はり)の瓶に入れ、紙で蓋をすると、末音はちらりとおゑんを見やった。
「少し、お疲れなのではありませんかの。このところ、何かとお忙しゅうございましたから」
「そうだね。少し忙(せわ)しくはあったね」
「少しどころでは、ございませんでしょう」
末音は火鉢にかかった鉄瓶を取り上げ、急須に湯を注ぐ。
「おや、茶を淹れてくれるのかい」
「はい。薬茶をお淹れしましょうかの。お疲れが取れますで」
「苦いのは御免だよ。青臭いのも嫌だね」
「まあまあ、童(わらべ)のようなことを仰いますの。お幾つにおなりです」
急須で心持ち冷ました湯を末音は湯呑に注(つ)いでいく。ゆっくりと、少しずつ、ひどく用心深い手つきだった。
「家屋の建て替えが無事に終わり、やれやれと思うたのに、おゑんさまのお仕事は一向に減りませぬのう。減るどころか、増えておるのと違いますかの」
「……仕方ないだろ。患者はいるし、赤ん坊だって……」
「そうですの。家屋を建て替えたことで、受け入れられる赤子の数は増えました。だから、おゑんさまの忙しさがさらに増したわけですがの」
末音が僅かに息を吐いた。
おゑんは医者だ。
女を診(み)る。とりわけ、子を孕んだ女を診る。子を孕み、けれど、さまざまな理由から産むことの叶わぬ女たちが、夜の暗みに身を隠すようにして、おゑんの許を訪れてくる。
産めない理由を泣きながら告げる女も、理由を話さず堕胎だけを頑(かたく)なに望む女も、子を産み生きていく未来に縋る女もいた。
どの女にも、おゑんは言葉を尽くす。
身体の内に宿った子を堕ろすことも、産み落とすことも命懸けであると。
「産むより、堕ろす方が身体を損なう見込みは高いかもしれないね。月満ちて子が生まれるのは自然の理の範疇だ。けれど、無理に身体の外に引きずり出すのは、その範疇から外れているんだよ。人も生き物。理から外れた者の命は危うくなる。そこんとこをもう一度、じっくりお考えな。焦ることはないよ。考える間は、まだ十分にあるんだ」
女たちの多くは、目を見開いておゑんを見る。おゑんの言葉が異国語ででもあるかのように、途方に暮れた顔つきになる。「考える……」と呟く者もいる。
考えたことなどなかったのだ。
産んではならない子を、産むことが許されない子を宿した女は、自分と赤子の行く末について考えたことなどなかったのだ。共に生きていける未来があるなどと、考えたことがなかった。本気で考えようともしなかった。
なぜだろうと、おゑんは時折、深く思案する。
女たちはなぜ、こうも容易(たやす)く、考え、足掻(あが)き、未来に進むことを捨ててしまうのか。諦め、抗わず、全てを受け入れてしまうのか。
そして、男はどこにいるのだろう。
女たちは大半が、一人でおゑんの許にやってくる。稀(まれ)に付添人がいても、たいていは母親か、お供の者かだ。男が傍らに寄り添うことは、ほとんどない。まるで、端(はな)からこの世には、いなかったかのように、気配すら感じさせない。
身籠った女は現から逃げられない。産むにしても産まないにしても、産めなかったにしても、その現を全て受け止めるしかないのだ。己の生身で、だ。男のように逃げられない。隠れも、誤魔化しもできないのだから。
男が、おゑんの前に姿を晒したのは、ほんの数例しかない。どれも、鮮やかに覚えている。小心で誠実な男、誠実を装おうとしている男、狼狽(うろた)え続けている男……そして、奇妙な男がいた。
もう五年も前になるだろうか。
嶋田髷(しまだまげ)の若い女と四十絡みの男がおゑんを訪ねてきた。親子だと言う。
次の正月で十五になる娘が子を孕んだ。始末してもらいたい。
短い挨拶の後、娘の父親はそう切り出した。父と娘二人して、おゑんの前に座り、子堕(こおろ)しを望んだのだ。本人も娘も地味な形(なり)ではあったが、裕福なのは見て取れた。父親は三朝屋政五郎(みささやせいごろう)と名乗り深川元町(ふかがわもとちょう)で小商いをしていると言ったが、店の場所も商いの程も偽りだろう。診察に関わりないので問い詰めたりはしない。かわりに、別の問い掛けをしてみた。
「お相手が誰かわかっているのですか」
「いや、わかりません。娘自身にもわかっていないようです」
政五郎は抑揚のない口調で、そう言った。それだけだった。娘をふしだらと罵ることも、忌み嫌う色を浮かべることもなかった。色白で柔和。頬も顎の線も丸く、目尻の皺まで愛嬌を宿している。つまり、いかにも商人向きの顔立ちだが、そこには何の情も浮かんでいなかった。空っぽでは、むろんないのに、一分の情も読み取れない。
人の顔とも能面とも違う。
背筋がすうっと冷えていくのを、おゑんは感じた。
相手の無表情に悪寒を覚えたのはいつ以来だろうか。知らぬ間に指を握り込んでいた。その指を解き、当の娘へと顔を向ける。
お秀という娘は、無言で俯いていた。僅かも動かず、息の音さえ抑えているようだった。
「では、ともかく診察いたしましょう。子がどこまで育っているか、まずはそれを知らなくちゃなりませんからね。お秀さん、こちらへ。三朝屋さんは、暫くお待ちください」
お秀を診察室に連れて行く。座敷を出るとき、一瞬だけ振り向いてみた。政五郎は正座のまま、石像のように座っていた。
「その床に横になってくださいな。大丈夫。手荒い真似は決してしませんから。怖がることはありませんからね」
柔らかく声を掛ける。お秀は両の指を握り締め、室の隅に立っていた。
(この章、続く)