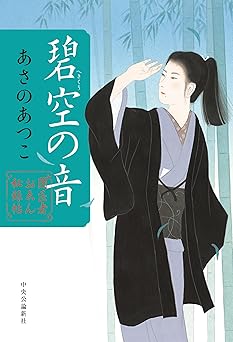「お秀さん」
傍らに寄り、そっと肩を抱く。おゑんの懐にすっぽり入るほど華奢な身体だった。
うん、これは?
疑念が胸を過(よぎ)る。
たくさんの女たちを診てきた。密に深く関わってきた。
だから、わかる。子を孕む前と後の、女の身体の変わり様を、ある程度までだが、指先で感じとることができる。
お秀を抱いた指の先には、硬く、乾いた肉の有り様が伝わってきた。
「お秀さん、嫌かもしれないけれど、あんたの股の間を診させてもらっていいかい」
お秀の身体が縮まる。さらに、硬く乾いていく。
おゑんは指の先に力を込め、娘の耳元に囁いた。
「嫌なら無理強いはしないよ」
お秀が顔を上げ、おゑんを見た。初めて、しっかりと目を合わせてきた。
その目を受け止め、囁きを続ける。
「あたしは、あんたの味方だ。あんたを損なうような真似はしない」
嘘ではない。本気だ。
どういう相手であろうと、どんな事情を抱えていようと、自分の許に流れ着いた女たちを損ないはしない。見捨ても、裏切りもしない。能(あた)う限り、守り通す。
お秀が身体を震わせた。また、俯けてしまった顔から、涙が滴る。まっすぐに、足元に落ちていく。
さて、この本気がお秀に伝わるかどうか……。
「お秀さん、あんた、まだ男を知らないね」
びくっ。指先に再度、震えが伝わってきた。
やはり、そうか。
もしやと思い、半分はったりで言い切ってみたが、的は外れていなかったらしい。
「そこに、お座り。今、お茶を淹れてあげるよ」
「いりません」
思いの外、はっきりと拒まれた。
「そうかい。じゃあ、座って、これをお飲み。薬だって思ってね」
小振りの湯呑に白湯(さゆ)を入れて、差し出す。
「一口だけでも、すすってごらんな。気持ちが、落ち着くから」
お秀は座りはしたが、まだ少しの間、躊躇(ためら)い、やっと湯呑を受け取った。ゆっくりと……というより、大層慎重な仕草で口に運ぶ。
「あ、これ……甘い」
「美味(おい)しいだろう」
「はい。美味しいです。この甘さって……」
「蜂蜜だよ。傷の手当てに使ったりもするのだけれど、こうやって白湯に溶いて飲むと、気持ちが緩むだろう。ふうっと、息が吐(つ)ける気がしないかい」
おゑんの言葉に誘われたかのように、お秀が吐息を漏らす。
そう、息を吐き、心身の力を緩める。そうすれば、新たな息が身の内に入ってくる。それで人は落ち着きを取り戻しもできるのだ。
「息が……吐けます」
「うん、よかった。嫌でないなら、全部、お飲み」
促すと、お秀は素直に湯呑の中身を飲み干した。
目元が仄かに明るむ。そうすると、歳に似つかわしい若さが匂い、華やかさが過る。一瞬だが生き生きとした気配を感じ、おゑんは胸の内で安堵の息を零(こぼ)す。
これなら、大丈夫かもしれない。
お秀は枯れているわけでも、空になっているわけでもない。自分の意思と想いをちゃんと持っているのだ。強張(こわば)った心が、それを閉じ込めていた。
「お秀さん、どうして、あたしのところに来たんだい」
お秀を座らせ、問うてみる。問われた相手は黙り込んだけれど、おゑんを拒んでいる風ではない。拒むのではなく、探しているのだ。どう、しゃべればいいか、その一言を探している。
ならば、焦らず待つしかない。
障子を通して、西日が差し込んでくる。政五郎とお秀は、まだ日のあるうちに、ここを、竹林を背負ったおゑんの家を訪れたのだ。
珍しい。おゑんの患者は大方が夜、とっぷりと暮れて、闇が全てを塗り固めてしまうような夜にやってくる。陽の光に身を晒すことを厭(いと)うかのように、闇に紛れようとするのだ。
西日は障子を薄紅色に染めている。庭から飛び立った小鳥の影が、くっきりと映り、その鳴き声が柔らかく響く。
「わかりません」
ややあって、お秀が呟いた。
「先生、あたし……おとっつぁんがわからないんです」
「わからないとは?」
「あたし……先生の言う通りです。男の人とその……そんなこと、したことなんてありません。一度も、ありません」
生娘というわけか。それなら、子を孕むなどあり得ない。
「なのに、おとっつぁん、このところ、あたしの顔を見ると『おまえは身籠ってるんじゃないか。もしそうなら、その子は産んではならんぞ』と言い出すようになって。初めは冗談かなと思っていたのですが、そんな風でもなくて……。だいたい、おとっつぁんは、冗談を言うような人じゃないし、顔つきも本当に真面目な感じで……あたし、どうしていいかわからなくて、怖くもあって……」
「おっかさんには、相談したのかい」
お秀がかぶりを振る。
「おっかさんは、あたしが十(とお)のときに亡くなりました。だから、今はおとっつぁんと二人っきりです。おとっつぁん……あたしのこと、すごく可愛がってくれています。いずれ婿を取って、店を継いでくれって……あたし、商いが好きで、お店も好きで、男だったらおとっつぁんの跡を継いで店を守(も)り立てたいと、ずっと思ってて、あの、でも、女でも商いには関わっていけるわけで、だから、あの、あたし商いを覚えようと本気で思ってたんです」
これまで、ほとんど口を開かなかったのが嘘のように、お秀はしゃべり始めた。蜂蜜湯が堰(せき)を取り除き、心の内が奔流となって流れ出したようだ。
「なのに、このごろ、おとっつぁん、おかしくて。変なんです。ほんとに変で……。あたしが子を孕んでいるだの、身重になっているだの、そんなことばかり言うようになって。あたし、怖くて……平太郎(へいたろう)、あの、うちの番頭なのですが、平太郎にも相談して……それとなく、諫めてもらおうと思って……」
お秀は、そこで口の中の唾を呑み込んだ。
「そしたら、おとっつぁん、平太郎を追い出しちゃったんです」
「追い出した? それは、番頭さんを辞めさせたってことですか」
「だと思います。あたし、よく、わからなくて……でも、平太郎があたしのところに挨拶に来て……。お別れだって。平太郎は、もうお爺さんで独り身で、あたしのことを孫みたいに思って、大事にしてくれてました。そんな人がいなくなるなんて、あたし、淋しくて、大泣きしてしまいました。あたしが相談さえしなければ、こんなことにはならなかったのかもと考えたら、よけい、悲しくて……」
「お秀さんのせいで辞めさせられたのかどうか、わからないだろう。それとも、番頭さんが、そう言ったのかい」
「いえ、平太郎は何も言いませんでした。でも、そうとしか考えられなくて。平太郎がいなくなって、おとっつぁん、ますます変になってしまい……子どもを堕ろせって、そればっかりで……あたし、怖くて、どうしていいかわからなくて、ただ、黙っていました。そしたら、今日、急にここに連れてこられて……それで、あたし……。もう、本当に頭が真っ白で、どうしていいかわからなくて……」
お秀はその場に、わっと泣き伏した。
何とも、奇妙な話だ。奇妙過ぎる。
おゑんは眉を寄せ、お秀の背中を見詰める。お秀の言ったことを鵜呑みにするなら、政五郎は常軌を逸している。明らかに、人の思案から外れている。
「お秀さん……えっと、この名前は本名かい。無理に言わなくていいけれど、もし、聞かせてもらえるなら、本当の名前を教えておくれな」
わざと、情のこもらない淡々とした口調で尋ねる。相手の乱れた心を静めるのには、寄り添うより慰めるより、この口調の方が効果があることも、多い。
「本当の名前です」
お秀は身を起こし、しゃくりあげながらも、はっきりと答えた。なかなか、しっかりした性根の持ち主らしい。少なくとも、己の不運や悲運を嘆き悲しむだけの女ではないかもしれない。とはいえ、まだ十五にもならない娘だ。父親の異変に怯え、泣き出すのも当たり前だろう。むろん、お秀の語ったことが真実であれば、だが。
「お秀さん、あたしに、あんたを診察させてもらえるかい」
「え……、でも、あたし……」
「わかっているよ。あんたが生娘だってことはね。あたしから、それをおとっつぁんに話させてもらっても構わないね」
お秀の唇が震えた。
(この章、続く)