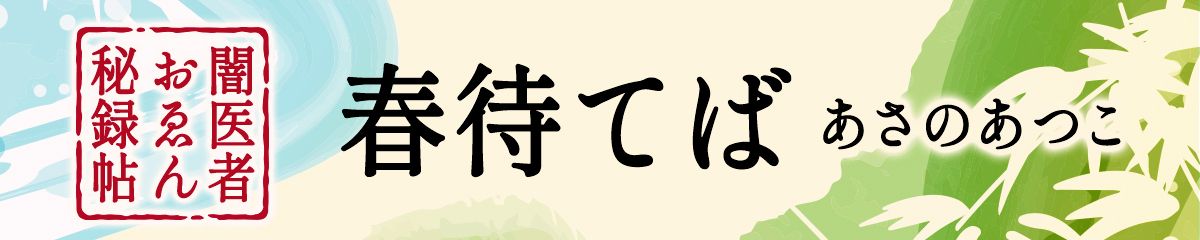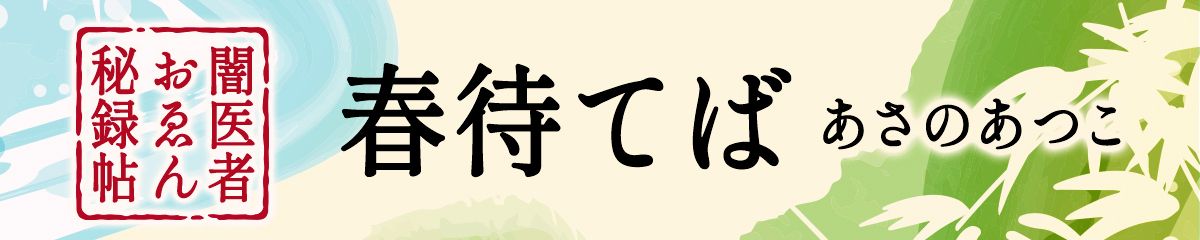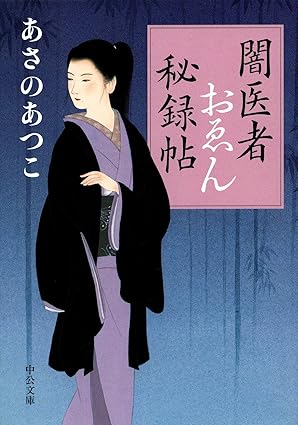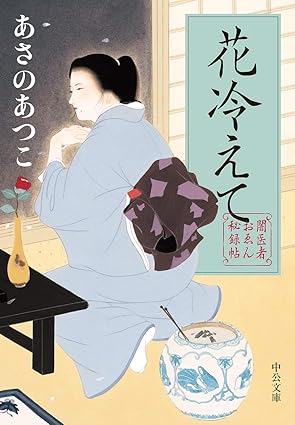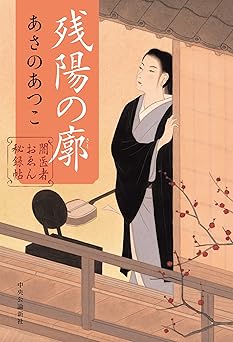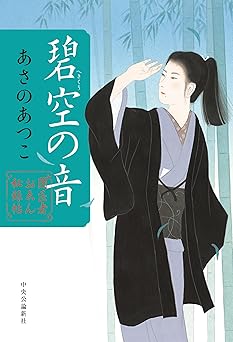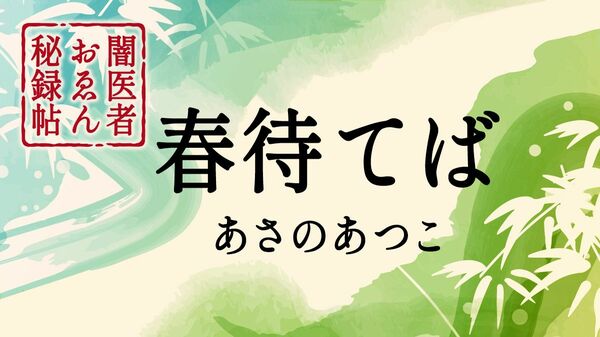
静寂(しじま)が部屋を包む。ややあって、政五郎が呟いた。
「さようですか。ええ……さようですか」
ほとんど、独り言だった。噛み締めるように何度も繰り返す。
「さようですか。真なのですか。だとしたら……」
呟き、目を閉じ、腕を組み、俯く。何事かを一心に思案している。そんな風だった。
おゑんは政五郎の前に座り、待つ。目の前の男が何を言うか、どう動くかを見極めるために待つ。政五郎がおゑんの言葉を信用せず、お秀を他の医者に診せようとするかもしれない。それは、お秀にさらなる苦痛を与えるだけでなく、剣呑(けんのん)な場に追い込みかねないのだ。医者が政五郎の意を酌んで、孕んでもいない子を掻き出そうとすれば、お秀の命が危うくなる。まさかとは思うが、政五郎の掴みどころのない様子は不穏であり、不安を掻き立てもした。そうならぬよう、お秀を守るための手立てを考えねばならない。それも、父親であるこの男の出方次第なのだ。
政五郎が目を開けた。
凪いだ眸(め)だった。
「先生は信用できます」
思いがけない一言に、おゑんは僅かに眉を顰めた。
「それは、どういう意味です?」
「そのままの意味ですよ。わたしの商人としての勘が、そう囁いておるのです。おゑん先生は信用して構わない相手だとね」
「あたしを信用するというのは、どういう意味になるのです」
政五郎の口元がふっと緩んだ。ここにきて、初めて見せた笑みだった。
「慎重ですな、先生。実に、用心深いお方だ」
「男を、それも、世の中がどういうものか知り尽くしている男を相手にしての用心なら、し過ぎるってことはありませんからね。よく、わかっておりますよ」
「ほお。そんな厄介な男たちをご存じなのですか」
「何人も存じております」
「おもしろい。またいつか、先生の来し方などをお聞きしたい。本気で思いますよ」
「あたしの来し方? そんなもの、三朝屋さんには退屈なだけですよ」
「そうとも思えませんが。是非にその機会を与えていただきたいものです」
「まあ。何とも困ったお方ですねえ」
お秀が身動(みじろ)ぎした。おゑんと父親を交互に見やり、迷い子のような心許ない顔つきになる。楽しげにやりとりしている大人たちに、戸惑っているのだ。
まるで古くからの知り合いの如くではないか、と。
「先生を信用いたします」
政五郎が繰り返した。
「先生のお診立ての通りだとすれば、わたしは間違っていた」
「ええ、あなたは間違っていました。間違って、お秀さんを苦しめたのです」
「お秀……」
政五郎が娘へと顔を向ける。お秀は胸の上で両手を重ね、父親と目を合わせた。
「すまなかった。おとっつぁんが愚かだった」
「おとっつぁん」
お秀の双眸から涙が溢れる。それを袖で押さえ、お秀は噎(むせ)ぶように泣いた。
「先生、これを診療代としてお納めいただけますか」
政五郎は懐から白い包みを取り出し、おゑんの膝元に置いた。十両の包みだ。
「多いですね。三両で十分ですよ、三朝屋さん」
「いえ、どうぞ、お納めください」
「もし、口止め料ということなら、それはいらぬ心配です。医者は患者についてのあれこれを外に漏らしたりはいたしません。何があってもね」
「口止め料などでは、ございません」
「では、忘れるための費(つい)え、でしょうか」
政五郎が瞬(まばた)きをする。お秀は涙に濡れた顔から袖を離し、身を震わせた。
「ここで、あたしが見聞きした全てを口外しないだけでなく、記憶から消してしまうこと。きれいに忘れること。そのための十両でしょうかねえ」
返事はなかった。「おとっつぁん」と、お秀が父を呼んだ囁きだけが耳に届く。
「それとも、二度と尋ねるなとの意でしょうか」
政五郎の片眉が心持ち、持ち上がった。
「さっき、あたしがお尋ねしたこと、三朝屋さんがなぜ、こんな思い違いをしたのかその理由、です。それを二度と尋ねるな。詮索もするな。触れるな。この十両を引き換えにして、そう命じておられるのでしょうか」
「先生」
政五郎が再び、手をついた。
「わたしは一介の商人です。先生に何であれ命じられるような者ではありません。それに、先生が金子(きんす)で動く方だとは、考えてもおりませんよ。ですから、ひたすら、お願いいたします。今日のことは、どうぞお忘れください。そして、何もお尋ねにならないでください。身勝手な願いと重々承知の上で、お願いいたします」
そのまま、平伏すように頭を下げる。おゑんは、お秀をちらりと見やった。お秀は胸を両手で押さえ、点頭した。懐には、あの地図が入っている。
そうかい、大丈夫なんだね。
「三朝屋さん、わかりました。この件はこれでお仕舞いとしましょう。もう何もお尋ねはいたしません。記憶は消すわけにはいきませんが、奥底に潜めておくことはできます。それで、よろしいですね」
一度上げた頭を、政五郎は先ほどよりさらに低く下げた。お秀も父に倣い、その場に平伏する。
解せない。この一件、どうにも解せない。
けれど、ここまでだ。これ以上、踏み込んではならない。
おゑんは父と娘に対し、礼を返した。
それで、終わった。
その後、お秀が訪ねてくることも、文を寄越すこともなかった。一度、深川元町の薬種問屋に出向いたさい、『三朝屋』の前を通った。味噌樽の看板が一際、人目を引く店だった。かなりの構えで、商いはよく回っているらしく、人々の出入りがあり、活気が伝わってきた。
おゑんは、その活気に背を押されるように速足で、店の前を通り過ぎた。
もう五年も前の出来事だ。
亭主であれ、父親であれ、情人(いろ)であれ、男が女の傍らにいた、極めて珍しい例の一つだ。そして、どこか奇妙な謎を含む一件でもあった。
花の香りが揺れた。
「どうぞ、召し上がられませの」
末音が薄手の小さな湯呑を盆ごと、おゑんの前に置いた。花の香りはそこから立ち上ってくる。中身は茶葉の緑ではなく、紅色に近い。
「おや、甘いね。蜂蜜かい」
「いろいろと入っておりますよ。藪肉桂(やぶにっけい)とか甘茶蔓(あまちゃづる)とか、その他諸々でございます」
「その他諸々ってのを、詳しく聞かせてもらいたいもんだ。おまえ、また、新しい薬茶をあたしで試そうとしてるね」
「ほほ、さすがに見通されましたか。けれど、お味はようございましょう。それに、疲れには効がございますよ。夜、お休みになる前にもう一杯、召し上がられませ。明朝の目覚めが違いますでの」
「そうだね。考えなきゃいけないことは多々あるけれど、考えても仕方ないことが多いものね。そのあたりの選(よ)り分けをしていかないと。身が持たないねえ」
家屋を改築し、座敷を増設し、行き場のない女や赤子をひとまず住まわせる場所を拵えた。これから、そこをどう活かし、回していくか思案のときだ。
まず、人手がいる。産みはしたが、育てられない、あるいは育てることを拒み通した女たちの子をここで育て、やがてしかるべき里親を探し出す。どんな生まれ方をしようと、生まれてきた子は幸せにならなければならない。それを担保するのが大人の責だ。血が繋がっていようといまいと、胸に抱いた子を我が子と呼び、慈しみ育てる。そういう里親を、赤ん坊と結び付けねばならない。
小さな命が損なわれないように、理不尽に奪われてしまわぬように、健やかに一日一日を過ごせるように守り通さねばならないのだ。
人手も金銭も要り用だ。今は何とか凌いでいるが、赤子が増えれば、いずれ尽きてしまう。悩みどころだった。
「まあ、でも、このところ落ち着いておりますから。それはそれで、ありがたいですの」
末音が自分も茶をすすり、ほっと息を吐く。
確かに、このところ、おゑんの周りは静かだ。女が運び込まれてくることも、赤子が死に脅(おびや)かされることもなかった。忙しいのは変わらぬままだったが、それでも、珍しいほど穏やかな日々が過ぎていた。末音が二度目の息を漏らす。
「いつまでも、このままならよろしいですがの」
「そうもいかないようだね」
「え?」
末音が口元を僅かに尖らせた。おゑんは湯呑を盆に返す。
「どうやら、また面倒事が来ちまったようだよ」
足音が聞こえたのだ。
密(ひそ)やかに、けれど、隠す様子もなく、一歩一歩近づいてくる足音だ。
おゑんは立ち上がり、気息を整えた。