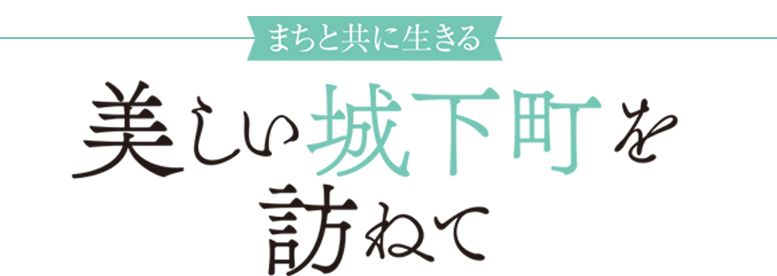上 石畳の通りに千本格子の家が立ち並ぶ。高岡市には、この金屋町のほかに山町筋、吉久(よしひさ)と重要伝統的建造物群保存地区が3ヵ所ある。
左下 金屋町発祥の高岡鋳物は一つ一つ異なる色を持つ。「鋳物工房 利三郎」にて。
右下 江戸時代からの商人町、山町筋(やまちょうすじ)に立つ菅野(すがの)家住宅。
富山県の北西部に位置する高岡市は、慶長14(1609)年、加賀藩(金沢藩)前田家2代当主前田利長がこの地に隠居城を築いた際に開かれた城下町だ。高岡の名は、『詩経』の一節、「鳳凰鳴(ほうおうな)けり彼の高き岡に」から、繁栄を願って付けられたと伝わる。利長は在城5年で他界し、翌年には一国一城の令により高岡城は廃されたが、3代当主利常の商業都市への転換を図る政策が成功し、高岡は「加賀藩の台所」と呼ばれるほどの隆盛を極めた。
利長が砺波(となみ)郡西部(にしぶ)金屋(かなや)から招いた7人の鋳物師(いもじ)に始まる鋳物づくりも、町の繁栄に一役買った。藩が鋳物師に厚い保護や特権を与えて住まわせたのが金屋町で、400年に及ぶ高岡鋳物の伝統を継承する町は今も往時の趣を色濃く残す。
神初(じんぱち)良子さん(81歳)は、高岡銅器伝統工芸士である夫の4代目利三郎氏とともに工房を守り、鋳物文化の案内役を担いながら、市の観光ボランティアガイドも務めている。
「昔は金屋町に15軒ほどあった鋳物工房も、今は数軒のみ。それだけに鋳物師の妻としての役割の大切さを日々感じています。ガイドや工房見学の受け入れを通して鋳物の町を紹介できるのは喜び。歴史あるこの町、この文化を誇りに思っています」




●交通:金屋町へは、JR高岡駅から徒歩約20分。
●お問い合わせ先:高岡市観光協会
TEL 0766-20-1547

-
提供/大和ハウス工業株式会社
大和ハウス工業について
詳しく知りたい方は→こちら