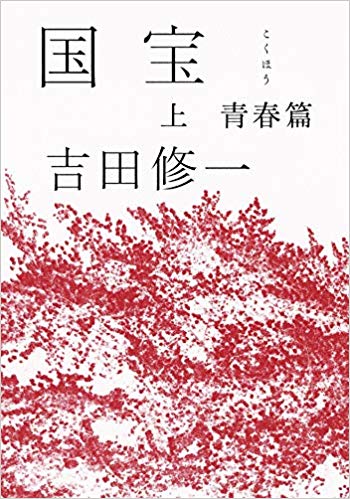*****
◆黒衣に身を包み、つぶさに見た歌舞伎の世界
東京五輪が開催される1964年から現代までの半世紀という時間の中で、歌舞伎界に生きる人間たちの歓喜と絶望を描いた『国宝』。作家生活20周年に本作を連載するにあたり、できれば自分がまったく未知の世界に飛び込んで、スケールの大きな物語を書きたいと考えました。
歌舞伎の知識は、それまでほぼゼロでした。舞台を見始めた頃は、歌舞伎特有のゆったりした時の流れに慣れずに席で熟睡することもしばしば(笑)。しかし四代目・中村鴈治郎さんのご厚意で自分用の黒衣の衣装を作ってもらい、毎月のように鴈治郎さんについて全国の劇場を回るうち、僕はすっかり歌舞伎の世界に魅入られてしまったのです。
朝、黒衣に着替えて一日を劇場で過ごす。楽屋から奈落から、地方の劇場と宿を結ぶ送迎バスにまで乗せてもらい、文字通り全身で取材することができました。舞台袖から間近に見る装置や衣装、鍛え上げられた役者の動き、鳴り物の音色……まるで「正月」のような、現実を忘れさせる異空間。これを小説で再現したい。その一心でした。
物語は、任俠の家に生まれながら当代一の女形へ上り詰める喜久雄と、彼が弟子入りをした大阪の歌舞伎の名門・花井家の御曹司、俊介の二人を中心に展開します。父が実子の自分ではなく喜久雄を後継者に選んだことで、身元を隠して旅回りの一座に加わる俊介。彼の留守中、喜久雄が歌舞伎界の因習に翻弄されながらも、自身の芸を極めていくさま。さらに二人が苦難を乗り越えて終生の友、好敵手としてふたたび同じ舞台に立つまで。彼らを取り巻く人々の栄光と転落、信頼と裏切りのドラマを描いていきました。
最も悩んだのが文体です。一人称か三人称か。物語にふさわしい語り口を探して、書き出す前の数ヵ月は試行錯誤を繰り返しました。そんなときテレビで、歌舞伎役者さんの丁寧で少し時代がかった口調を聞いて、ああこれだ、と。試してみると、一行目から「これから別世界の話が始まる」というイメージが立ち上がって、物語が一気に進みました。
◆一流とは何だろう
これまでの伝統芸能を扱った小説には、高尚で難しいイメージがありました。でも僕はまったく逆をやりたかった。歌舞伎の演目は超エンターテインメントですし、演出も派手でわかりやすい。それと同じく、泣かせる場面は徹底的に泣かせ、登場人物が死ぬ場面はけれん味たっぷりで大げさに、とにかく「ベタ」にやってみようと。
書き進めるなかで心に浮かんだのが、「一流とは何だろう」という思いです。一流の歌舞伎役者である喜久雄が「どんな景色を目にしたら最も幸せなのか」ということを、ラストシーンまでずっと僕は考えていました。
連載中には、読者から多くのお手紙をいただいて。僕にとって新鮮だったのは、喜久雄や俊介などの登場人物に、「ご贔屓」にしてくれるファンがついたことです。また表舞台に出るのは男性ですが、それを裏で支える女性たちに共感してくれる人も多かった。
もし自分が歌舞伎俳優だったら? コスプレとしては「助六」とかの派手な衣装を着てみたい。演じるのなら、落ちぶれて、なじみの芸者のところに転がり込む若旦那がいいですね(笑)。もし本書をきっかけに歌舞伎に興味を持ち、気軽な娯楽として劇場に足を運んでくれる人が増えたら、遅れてきた歌舞伎ファンとしても大きな喜びです。