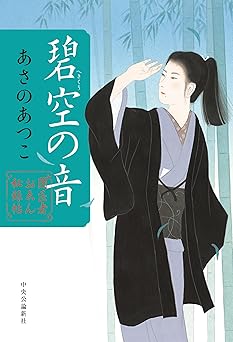「先生、おとっつぁんと話をしてくれるの?」
「伝えなきゃいけないことは、伝えるさ。本当のことをね」
お秀が手をつく。額を畳につけるほど深く、頭を下げる。
「お願いします。先生、どうか、おとっつぁんに伝えてください。そして、そして……できるなら、おとっつぁんを治して。前のおとっつぁんに戻してください」
「それは無理だね」
おゑんの一言に、お秀は顔を上げ、眉を寄せた。苦し気な表情だ。
「あたしは医者だ。病や傷の治療ならできる。けどね、人の心の歪みや変容を正すことなんて、できない。無理なんだよ、お秀さん」
「先生、それじゃあ、あたしはどうすれば……」
おゑんは、娘の肩に手を置いた。
「ここまでは、どうやって来たんだい」
「歩いてきました。おとっつぁんが地図を持っていて……あの、以前、先生に掛かったことのある人から、先生の噂とお家(うち)の場所を聞いたんだとかで、その人の描いた地図を持ってたんです。それが、わかり辛くて、何度か道に迷いました。でも、あたしは、ただ、おとっつぁんの後ろからついて歩いただけです。どこに連れて行かれるか、ぎりぎりまで教えてもらえなくて……」
「そうかい。じゃあ、これを」
紙入れから一枚取り出し、お秀に渡す。
「これは?」
「おとつつぁんが持っているものより、よほど詳しく、わかり易い地図だよ。近道も描いてある。これがあれば、一人でここに来られるはずだ」
「地図」
お秀の喉元が動いた。息を呑み込み、手にした紙を見詰める。
「これから、あんたの身体を診させてもらうよ。その上で、おとっつぁんと話をする。あたしが話せることは、包み隠さず伝える。けれど、それで、おとっつぁんがどう変わるか、何も変わらないのか、あたしには判じられないんだ」
こくり。お秀が頭を前に倒した。子どものような頷き方だった。
「もし、お秀さんが耐えられないような何かがあったら、ここに逃げておいで。真夜中でも、夜明け方でも構わない。それも難しいようなら、文(ふみ)を届けておくれ。ただし、そのときは、自分がどこにいるか、はっきり記してもらいたい。わかったね」
「それは……先生が助けに来てくれるって、そういう意味?」
「そういう意味さ。お秀さん。あんたに助けが要(い)り用なら、あたしは、あんたを助ける。決して、見捨ても、見放しもしない。約束するよ」
お秀の唇から、細い息が漏れた。
「どうして? どうして、先生はあたしを助けてくれるの。赤の他人なのに」
「患者だからだよ」
おゑんは、お秀の手の上に自分の手を重ねた。
「お秀さんは、あたしの患者だ。だから、救うために力を尽くす」
これまでも、そうしてきた。
ただ、力の限りを尽くしても、救えなかった患者は多くいる。必死に手を伸ばしても、届かなかった。生きる側に引き戻せなかった。そういう女たちが、大勢いたのだ。それでも、手を伸ばす。腕でも、脚でも、髪の毛であっても掴み、死に流されぬように踏ん張る。
これからも、そうしていく。
「でもね。お秀さん、あんた次第なんだよ。当人である、あんたがうずくまっていては、助けようがないんだ。何かあったとき、身体が危うくなったときだけじゃなくて、心がぎりぎり追い詰められたと感じたときも、あたしを頼れるかい。ここまで、逃げて来られるかい。報(しら)せてこられるかい。それができないと、あたしは動きようがないんだ。いいね、お秀さん。うずくまって泣いているだけじゃ、手の差し伸べようがないんだよ」
差し出した手を握り返してくれなければ、どうしようもない。握り返す前に諦めてしまう女たちが、うずくまったまま助けを呼ぼうともしない女たちが、どれだけいたか。
歯痒い。
女たちも、女たちに信じ切ってもらえなかった自分も、歯痒い。
「……先生」
お秀は手の中の地図を握り締め、首を伸ばし、ゆっくりと首肯した。大人の頷き方だ。
「ありがとう、先生。あたし、今、すごくほっとしてます。何かあったら、必ず、必ず、先生に助けてって言う。ここまで走ってくる」
地図を丁寧に畳み、お秀はそれを胸元に仕舞い込んだ。
「うん、そうしな。逃げ場があるってことを忘れないでおくれ。それでね、お秀さん。念のために、おとっつぁんの店の名前と場所を教えちゃくれないかい」
「え? でも、それは、さっきおとっつぁんがお伝えしましたよね。深川元町の味噌、醤油問屋『三朝屋』だって」
顎を引く。意外な心持ちがした。
「あれは、本当だったのかい」
「はい、本当です。本通りの真ん中あたりにありますよ。大きな味噌樽の看板が掛かっているから、目立つの。すぐにわかると思うわ」
「そうかい」
とすれば、政五郎は騙(かた)ってはいなかったわけだ。何を誤魔化そうとも、隠そうともしていなかった。ありのままを、おゑんに告げた。真実をしゃべった。
おゑんは、そこを見誤ったのだ。
見誤ることは、ままある。けれど、こんなにも、気持ちが引っ掛かることは珍しい。
どうも、ズレている。
これまで、おゑんが出逢ってきた者とも事とも、僅かにズレているような気がする。
どこが、どんな風にズレている? 外れている?
わからない。だから、引っ掛かる。
おゑんは立ち上がり、診療用の上っ張りに手を通した。
「お秀さん、そこに横になって。診察させてもらうよ」
お秀の顔が強張る。
「股を開いてもらうから、嫌かもしれないけど、すぐに済むからね」
「痛い? あたし、痛いの苦手で……」
「そうだね。痛みが得意って人は、なかなかいないね」
ここで、少しだけ笑んでみる。
「大丈夫。そんなに、痛くはしないよ。大切なところだからね、傷をつけたりしたら大事だ。そんな真似はしないから身体の力を抜いて、楽にしておいで」
「はい」
お秀は素直に、夜具の上に仰向けになった。その腰の下に、木綿の布と油紙を重ねて敷く。
「うん。もう少し緩んでおくれ。大丈夫だから、直(じき)に終わるからさ」
おゑんの一言、一言にお秀は律儀に「はい」と答え、身体の力を抜いた。
診察には、さほどの時間はかからなかった。
お秀を連れて、政五郎の待つ座敷に戻る。政五郎は先刻とまったく同じ姿勢で座っていた。一寸も動いていなかったかのようだ。
「三朝屋さん、お秀さんの診察、終わりましたよ」
そう告げると、政五郎は緩慢な仕草で低頭した。
「お手数をおかけしました。ありがとうございます」
「いえ。これが、あたしの仕事ですから。どうぞ、お顔をお上げくださいな」
政五郎が身を起こすのを待たず、続ける。
「お秀さん、まだ破瓜(はか)されてはおりませんね」
政五郎が息を吸い込んだ。そのまま、口を閉じる。
「当たり前ですが、子を孕んでもおりません。あたしが診たところ、もう三、四日もすれば月のものが訪れると思いますよ。ですから、今回は、三朝屋さんの思い違いです」
政五郎は暫くの間、無言だった。おゑんに言い返すことも、問い質すこともしなかった。
「三朝屋さん、なぜです」
問うたのは、おゑんの方だった。
「なぜ、こんな思い違いをなさいました。なぜ、お秀さんが子を孕んだと、勘違いなさいました。その理由(わけ)、よろしければ、お聞かせください」
政五郎が真正面から、おゑんに目を向ける。こちらを射貫くほど尖ってはいないけれど、柔らかくもない。甘さのない目つきだった。商人が品の目利きをするような、どこか冷えた眼差(まなざ)しでもあった。
「先生、それは真でございますか」
おゑんから目を逸らさぬまま、政五郎が口を開いた。
「お秀は、真に男を知らぬ身体であったのでしょうか」
「はい。あたしが診察いたしました。間違いありませんよ、三朝屋さん」
おゑんも三朝屋政五郎の視線から逃げない。きちんと受け止める。二人は黙ったまま互いを見据えていた。お秀は部屋の隅で、置物のようにじっとしている。
「あたしはね、三朝屋さん」
一息吐き出し、おゑんは帯に沿って手を滑らせた。そして、背筋を伸ばす。
「これまで、とんでもないしくじりも、診立て違いもしてきました。苦い思いも、散々味わってきましたよ。でも、お秀さんへの診立ては一毫(いちごう)の過ちも犯してはおりません。ええ、真です。お秀さんは生娘です」
(この章、続く)