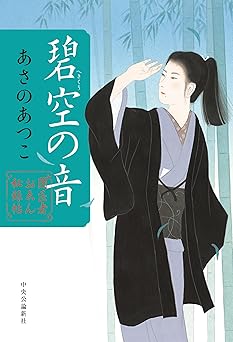「ご存じの通り、あたしは美濃屋さんに乞われて、月に一度か二度、花魁の許に通っています。揉み治療や灸も施すし、鍼(はり)も打ちます。診立てによっては薬も調合します。そして、花魁安芸ではなくお小夜さんの話を聞きます、思ったこと、感じたこと、昔話、行く末の話、今の想い……ええ、さまざまな話をしますよ。吉原の中で、お小夜として、ありのままをしゃべれる相手は、あたしだけなのです。しゃべれば気持ちが落ち着き、抱え込んでいた悩みや疲れが、多少なりとも軽くなります。内に溜めるのではなく、外に流し出す。それこそが肝要。心身の健やかさを保つには、案外効があるんです」
「つまり、花魁は先生相手にしゃべって、身の内を軽くしているってこってすか」
「ええ。害になるものが、例えば腐った魚とか毒のある茸とかね、そういうものが入ってきたら、身体はそれを外に出そうとするじゃありませんか」
甲三郎が瞬(まばた)きする。右手で腹の辺りをゆっくりと擦(さす)る。
「それは反吐を吐いたり、腹を下したりって意味でやすね」
おゑんはわざと苦笑してみる。
「その通りです。でも尾籠(びろう)な話になるので、わざと言葉を暈(ぼか)したのに、身も蓋もない言い方をしちまうんだから。困ったお人ですよ」
「先生には、暈しは似合いませんや。いつだって単刀直入、ずばりと切り込んでくるのが、おゑん先生じゃねえですか」
真っ直ぐに切り込むだけでは、生き残れない。上手く暈すのも、軽く往(い)なすのも生きるための方策になる。甲三郎なら百も承知だろう。承知の上で、あなたには似合わないと告げてきた。おゑんの冗談めかした軽口に、真正面から答えてきた。
ずい分と青臭い真似をする。
甲三郎の若い未熟さを垣間見た気がした。それを微笑ましいとも清々しいとも感じない。むしろ、若い未熟さを抱えたまま、他人を斬り捨てられる男に異形を見る。
おゑんは眼差しをずらし、小さく息を吐いた。
「あたしが言いたいのは心も身体と同じってことなんです。心を害するものが溜まれば、それを吐き出さねば心そのものが病になる。身体より心の病の方が厄介で治り辛いってことも往々にしてあるんです。だから、吐き出してもらう。嫌な思い出も、悲しい出来事も、傷だらけの来し方も、重すぎる秘め事も、抱えきれない分を吐き出せるよう手を貸す。それも、あたしの仕事の内だと思っています」
やや早口で、そしていつもより饒舌に語る。
「お小夜さんは、あたしを頼りとして、心の内を打ち明けるんですよ。だから、あたしを待っている。それが本当のところ、真実ってやつですよ。ただね、次に美濃屋さんに伺うのは七日ほど後です。でも、お小夜さんは、その七日が待てなかった。あたしは、そこが不思議でしょうがないんです」
これは本音だ。お小夜は粘り強く、芯の強い女だ。待ち焦がれた相手が七日後に来るとわかっていれば、その七日をじっと耐え忍ぶ。それができる者でもあった。
「そしてね、文には、逢いたいとは書いてありますが、なぜ、逢いたいのかについては一言も書かれていません。ねえ、甲三郎さん、お小夜さんは、この文の中身が美濃屋さん、ひいては川口屋さんの目に触れることまで考えたんじゃないでしょうか」
「あっしが文を惣名主に渡すかもと、疑ったってこってすか」
「疑ってはいなかったはず。甲三郎さんが、預かった文を他人に見せるようなお人ではないと、お小夜さんは、十分にわかっています。わかっていたから、託したのでしょうからね」
再び、甲三郎が眉を寄せた。ほんの微かだが、戸惑いの色が眼の中に浮かぶ。
「疑ってはいなかった。でも、用心したのですよ。万が一を恐れた」
「万が一?」
「ええ、例えば川口屋さんからその文を見せろと迫られる。そうなることを恐れた」
惣名主からの命を、首代が拒めるわけがない。
甲三郎が首を竦める。
「お小夜さんは万が一のときを考えて、逢いたいとしか書かなかった。読まれても差し障りのない恋文として認(したた)めた。そうじゃないですかね」
「いや、先生。花魁が客でもない相手に恋文を送る。十分に差し障りがありまさぁ」
今度は、甲三郎が苦笑する。
「お言葉を返すようで申し訳ねえですが、あっしはやはり、この文は花魁の心そのままを認めたものだと思いやすぜ。何かあったのかどうかまでは、わかりやせんが、花魁は先生に逢いたくてたまらなくなった。七日を耐え忍ぶことができなかったんでやすよ。それで、想いのままに文を認めた。そう思うんですけどねえ」
甲三郎の眼差しは、のんびりとした口調とはうらはらに鋭さを秘めていた。
「何でですかねえ、先生」
空になった湯呑を握り締め、甲三郎が呟く。
「何で、そんなに事の裏の裏を探るんです。底の底に沈んでいるものを引きずり出そうとするんでやすか。あっしも、それなりに人を見てきたつもりじゃおりやす。けど、先生みてえに強欲な者に逢ったことはありやせん。人の密(みそ)か事を知りたくてうずうずするとか、化けの皮を剥がしてやりたくて我慢できないとか、そういう手合いは掃いて捨てるほどいやした。吉原に限らず、大門の外、どこにだってごろごろしてやす。けど、先生は違う。まるで、違う。いつだって、人の本性に手を伸ばそうとする。損得でもなく、信念とかでもない。そこが、あっしにはどうにも、わからねえんで。先生には、人ってもんはどんな風に見えてんでやす。いろんな物がごちゃごちゃ詰まった箱みてえなもんでやすか、それとも、さっきの話だと底無しの沼みてえに見えてるんでやすかね」
おゑんも首を竦めてみせる。
「人は人ですよ。人としか見えていません。でも、その人こそがおもしろいじゃありませんか。殺し合いもするし、助け合いもする。残忍だし、卑怯だし、自分勝手でもある。なのに、優しくて、矜持を持ち、他人を慮(おもんぱか)ることもできる。おもしろくて、不思議でしょう。だから、惹かれるんですよ。その正体を掴みたいって引き込まれてしまう。ふふ、性分ですよ。あたしの性分、それだけのことです」
風が強くなった。障子戸がかたかたと鳴る。寒さがじわりと増す。
春はそこまで来ていたはずなのに、どこか遠くに追いやられてしまったのだろうか。
「その性分はどうやって作られたんで」
甲三郎の指がさらに強く、湯呑を握った。
「先生は、これまで、どんな生き方をしてこられたんでやすか」
「聞きたいですか」
「聞きたいです。どうしようもねえぐれえ、聞きたいと思いやすよ」
ふっと波の音が耳朶(じだ)に触れた。
いや違う。これは、ただの風音だ。故郷に響いていた海鳴りとは違う。
「あたしの来し方なんて知ったって、何の得にもなりませんよ。つまらない、ごくありふれた話に過ぎませんからね」
風の音、海鳴り。そして、悲鳴と叫び声。北国の故郷から、母と末音と三人で江戸まで逃げてきた。母は亡くなり、おゑんは今も生きている。
この男は、あたしの何を知りたいのだろう。
どう生きてきたか。何を見てきたか。信じてきたか。誰を憎み、誰に心を許してきたか。そんなことを知りたいのだろうか。
「甲三郎さん」
「へい」
「お小夜さんに、この嵐が収まり次第逢いに行くと、そう伝えてもらえますか」
「承知しやした」
甲三郎が立ち上がろうとしたとき、廊下に軽やかな足音が響いた。障子戸が横に滑り、お春の顔が覗いた。お春は、目が回るほど忙しいにもかかわらず、このところ少し肥えた。顎が丸くなり、頬がふっくらとやはり丸くなった。外見の変化は、お春の美質をくっきりと際立たせたとおゑんは感じている。
柔らかさと円(まろ)やかさ。お春にそっと触れられただけで、泣き止む赤子がいた。痛みが和らぐと喜んだ患者がいた。目の前の首代も、目元口元を緩ませている。
「お春さん、お久しぶりでやす」
「まあまあ、本当にね、末音さんから甲三郎さんがお出でになったと聞いて、走って来たんですよ。逃げられる前に捕まえとかなくっちゃって、慌ててね」
「いやあ、逃げやせんよ。お春さんから逃げ切れるわけもねえし」
「まっ、それはどういう意味かしらね」
二人の笑い声を耳にしながら、おゑんは廊下に出た。
お小夜さん、何がありました。あたしに伝えねばならない何があるんですか。
吉原に囲い込まれた女に問うてみる。
風が重みと湿り気を帯びた。家の裏に広がる竹林がざあざあと葉音を立てる。
やはり海鳴りを思わせる音だった。