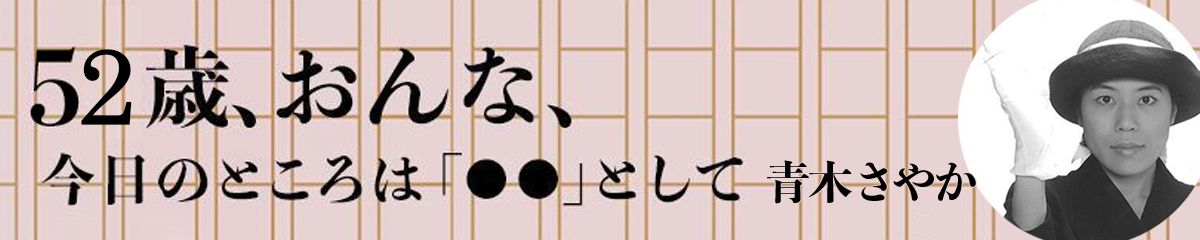世の中には、がんの話題が溢れている
親も祖父も、がんだった。いつかわたしもがんになるかもな、と思ってはいたが、実際診断をされた時のインパクトは大きかった。心から笑うということができなくなった。
その時、闘病中で存命だった母には知られたくなかった。心配をかけたくなかったとも言えるし、当時母とはうまくいっていなかったので、母がわたしの病気で自分を責めたりすることすら、許したくなかった。ともかく、この時母のことを考える余裕がなく、蚊帳の外にいて欲しかった。
母だけでなく、がんになったということはできれば誰にも知られなくなかった。欠陥があると思われるのでは、とか仕事が減るのでは、とか同情されるのでは、とか、知られていいことなんて一個もないと思った。
がんだと隠して生活をしていると、世の中には、がんの話題は溢れていることを知った。「あの人がんらしいよ」「マジで!」的な会話は多く、その度、胸がぎゅっとつかまれる思いがした。あゝそうだよな、こう言われるよな、これは隠しておかなくては、それがいい。だから、わたしは、そんな時はもちろん黙ってやり過ごしていたし、少しずつ嘘をつきながら他人と付き合いはじめた。それはそれで、別に悪くはなかった。
両親が他界し、『母』という自伝的小説を出すにあたり、わたしは迷ったが、がんの手術をしたことを書くことにした。主人公のわたしを表現するには、とても大きな出来事だったからだ。