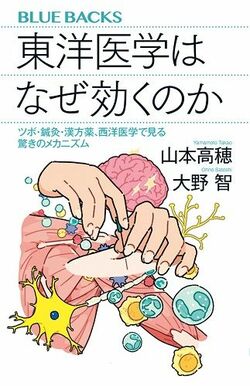現在使われている鍼の種類
そして、鍼灸が朝鮮半島を経由して日本に入ってきたのは6世紀頃とされており、飛鳥時代の701年に制定された大宝律令では、鍼が国の医療として定められました。
以後、1300年以上にわたり日本で独自の治療法や器具などが発展し、現在に至っています。
ちなみに現在、日本で主に使われている鍼は、太さ0・2ミリメートルほど、長さ4〜5センチメートルほどの極細で、管を使って皮膚や筋肉に刺し入れるタイプです。
症状や目的にもよりますが、深い場合は筋肉まで鍼を刺し入れます。
ほかにも、画鋲(がびょう)のような細く短い鍼をシールで貼り付ける円皮鍼(えんぴしん)や、金属の突起で皮膚を刺さずに刺激する接触鍼などのタイプもあります。