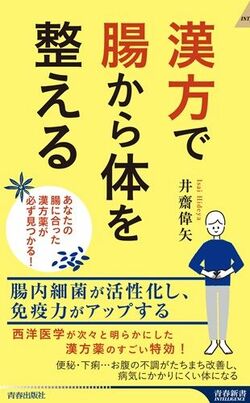従来の薬理学ではあり得ない考え方
一方、漢方薬は咳の状態によっていろいろな処方があります。その人に適した漢方薬が見つかれば、一服でピタリと咳が治まります。そこが漢方医の腕の見せどころで、一服で治らないときはどんどん別の薬に変えていきます。
新薬は脳の「咳中枢(脳にある、咳を出させるスイッチ)」を抑えるだけで、肺で起こっている炎症には効きません。事件は現場で起こっているわけですから、肺の炎症を鎮められなければ咳は止まりません。漢方薬は肺のほうに働いて、その炎症をさっと抑えてしまうのです。
前記した咳に苦しんでいた方は、効かない新薬を飲み続けて1か月苦しんだものの、最終的には治った。これも体に治す力が備わっていることを示しています。
仮にこの人が漢方薬を飲んだとしても、結局のところ治すのは自分に備わっている力です。それでも、漢方薬を飲むことでもっと早く咳を鎮めることはできたでしょう。
漢方薬が治すのではなく、それを飲んだ人が変わる。こうした漢方薬の働きについて、薬理学の先生方にお話しすると、「今までそんなふうに考えたことがなかった」「頭が真っ白になった」とよく驚かれます。そのくらい従来の薬理学ではあり得ない考え方なのです。