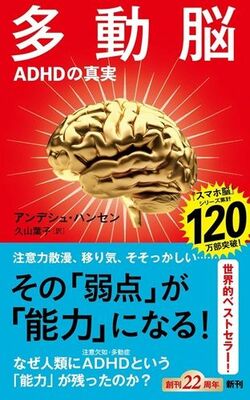「創造性」とは「正しい方向に向かった衝動」
考えてみるとおかしなことではない。クリエイティブになるための前提を良くする努力はできても、アイデアというのは注文して届くものではない。ただ頭に浮かぶもの──衝動のように。
しかも衝動の制御が苦手なこととクリエイティブな発想を行動に移す能力には関連があるという。アイデアをただ考えているだけの段階で置いてきぼりにしないからだ。ハーバード大学の精神医学の研究者ジョン・J・レイティも創造性を「正しい方向に向かった衝動」と呼んでいるくらいだ。
脳は常に様々な衝動を抑えている。スマホを手に取りたい、「そのネクタイはダサい」と正直に相手に伝えてしまいたい、退屈過ぎて会議室から出ていきたいといった衝動を抑えているのだ。もちろんスマホを手に取ったり人を侮辱したりしないようにするにこしたことはないが、衝動を抑制できる人はクリエイティブな考えも抑制してしまっている可能性がある。
ジョン・J・レイティ流に言えば、衝動性を「正しい方向に向かわせる」ことができていないのだ。思考の流れを増やすリーキー・アテンションのせいで頭の中に10個も考えがあって困るのと同時に、衝動を抑える能力の不足がクリエイティブな衝動を抑えないという〈強み〉にもなる。コインには必ず表と裏があるのだ。
ではADHDの3つめの大きな特徴、多動についてはどうだろうか。それも創造性に関わってくるのだろうか。多動だとエネルギーに溢れて、長く作業を続けられるという利点がある。創造性に関する研究でも判明していることだが、クリエイティブな作業というのは生まれ持った才能や天から突然降ってきたような発想よりも多大な努力と時間によって実を結ぶ。
アメリカのラッパーでADHDのウィル・アイ・アムも「多動がクリエイティブな作業の役に立っている」と発言している。「ADHDのH(多動)を役立てられるような仕事の仕方を身につけたんだ。おかげで地球上の誰よりも長時間働くことができる」
ADHDにはじっとしていられない、実行力がある、リスクを恐れない、権威や伝統にひれ伏すことがないという特徴がある。既存のルーチンや仕事の作業手順がうまく機能しない時にも「でも今までずっとそうしてきたから」では納得せず、よりよい方法を探そうとする。
実行力がある、既存のものに疑問を呈する、じっとしていられない、リスクを厭わない、他の人がやっていることを当たり前だと思わない──そういった特徴はまさにクリエイティブな人の特徴でもあるだろう。