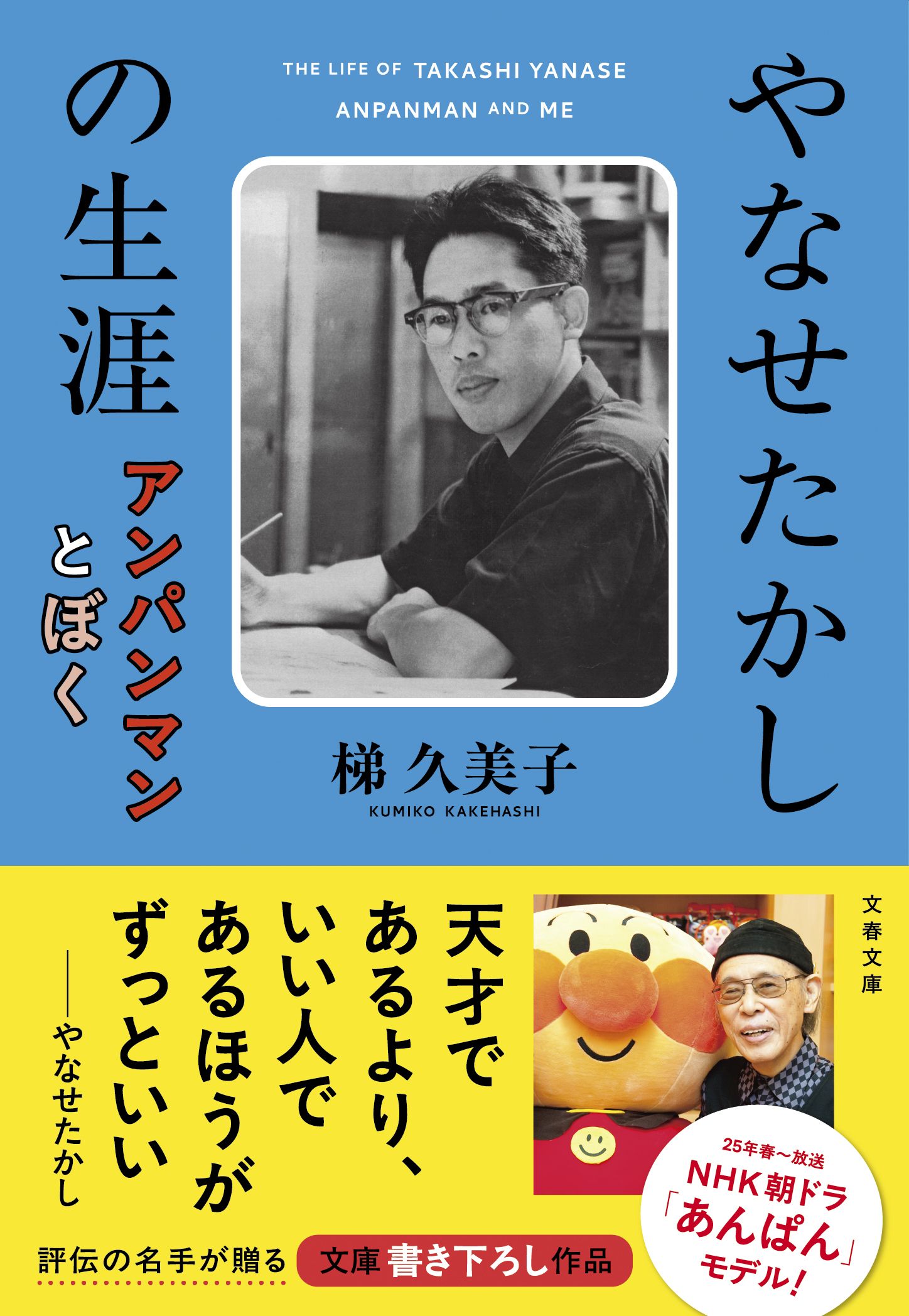こっそりあめ玉をくれたのは
当時、柳瀬家には住み込みの若いお手伝いさんがいた。彼女は「お兄さんなのに、おかわいそうです」と嵩に同情し、ときどきこっそりあめ玉をくれた。
ある夜、彼女はみなが寝静まったのを見計らい、嵩をおんぶして、町はずれの駄菓子屋につれていってくれた。事前に頼んであったらしく、駄菓子屋は夜中でも店を開けていて、嵩は、伯父や伯母からは禁じられていた駄菓子を買ってもらった。
「朝や」という名前だったそのお手伝いさんのことを、嵩はのちに詩に書いている。
そのちいさな駄菓子屋は
夢の天国だった
ぼくの記憶は非常にあいまいだ
なにしろぼくはねぼけていて
ゆきもかえりも夢うつつだった
でも
あたたかい朝やの背中
朝やの背中で見た
空いっぱいの星
こぼれおちた流れ星
ぼくは今でも忘れない
弟よ
君はしらなかったろうね
朝やの星が美しかったことを (「朝やの星」より)
さびしい思いをしている人にしか見ることのできない景色がある。幼少期の嵩にとって、朝やの背中で見た空いっぱいの星がそれだった。
嵩の人生には、つらいときや不遇なとき、不思議と力になってくれる人があらわれた。もともとは縁もゆかりもない他人が、なぜか助けてくれるのだ。まだ十代の少女だった朝やは、その最初のひとりだった。
※本稿は、『やなせたかしの生涯 アンパンマンとぼく』(文春文庫)の一部を再編集したものです。
『やなせたかしの生涯 アンパンマンとぼく』 (著:梯久美子/文春文庫)
ノンフィクション作家・梯久美子が、綿密な取材をもとに知られざるエピソードを掘り起こした「やなせたかし」評伝の決定版。著者はかつて『詩とメルヘン』編集者として、やなせたかしのもとで働き、晩年まで親交があった。愛と勇気に生きた稀有な生涯を、評伝の名手が心を込めて綴る感動作。