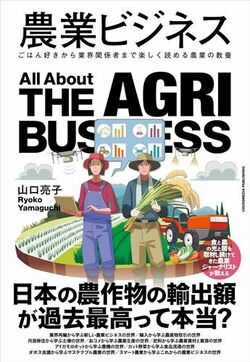高温障害の代表的な例
高温障害の代表的なものを紹介すると、まず水稲では出穂期から2週間ほどの気温が高いと粒が白濁し、炊くと糊状になる「白未熟粒」が発生します。出穂直後に高温と乾燥した状態になると、粒が割れる「胴割米」も生じてしまいます。
果樹の場合は、果実の着色が進む時期に平均気温が高いと、色が悪くなります。緑色の葉緑素を消失するには低温が必要で、かつアントシアンやカロテノイドといった果実を色づける色素は、高温で合成が妨げられるからです。加えて、直射日光を強く浴びるなど1日でも果実が高温の状態に置かれると、黄色や茶色に変色してしまう日焼けが起こります。
畜産の場合、家畜は夏場に餌を食べる量が減りますが、高温だとそれがより顕著になります。乳量が低下したり、ニワトリが卵を産まなくなったり、肥育(肥え太る)速度が落ちたりします。人間と同じで熱中症にもかかり、ひどい場合は死に至ることもあるのです。
野菜では、秋に気温が高いと生育が前倒しになり、冬に収穫するはずのものが早まってしまいます。秋に価格が大暴落し、その反動で品薄になる冬に価格が高騰するという状況が、最近繰り返されるようになっています。
病害虫にも温暖化で変化が生じ、水稲では高温下で発生しやすい紋枯病(病斑が現れ株が倒伏しやすくなる)が増えたり、害虫ならより南に生息していた種が北上したりしています。そんな状況が各地で頻発しているのです。