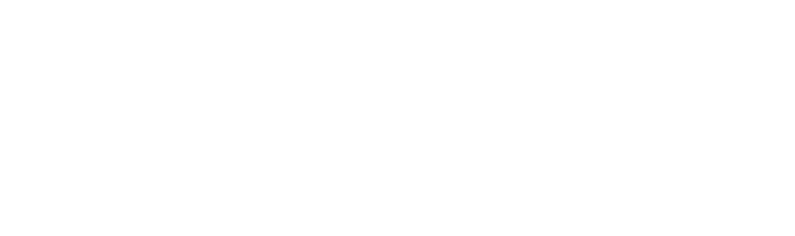人が持つ潜在的な「黒さ」を表現
そのうち、女性たちの陰の部分が色濃く描かれるようになります。『女性自身』に連載された名作『波の塔』も、お嬢さん探偵が主人公の小説と思いきや、不倫カップルの物語に焦点が当たるのです。
清張さんといえば、悪女モノがよく知られています。『黒い画集』『黒い福音』など、タイトルに「黒」がつく作品も多いのですが、人間の心の「黒さ」を的確に描くのが本当にうまい。やはり陰のある女性のほうが、書いていて楽しかったのではないでしょうか。
「夫が死んだらいいな」とか「このお金が自分のものになったらいいのに」など、実際に行動には出ないまでも、誰しも後ろ暗い思いを持っているはず。自分ではできない行動を登場人物が代わりに行ってくれると、読者はスカッとしたのかもしれません。
人が持つ潜在的な「黒さ」は、昔も今も変わらない。だから清張さんの小説は愛され続け、ドラマ化されるのではないでしょうか。
清張さんが一番多く執筆した女性誌は、たぶん『婦人公論』だと思います。『砂漠の塩』『霧の旗』などの長編のほか、『影の車』など連作短編も書いている。
『女性自身』は当時、20代のOL向けだったので、若い女性が夢を見られるような恋愛サスペンスものが多い。一方、『婦人公論』では、たとえば夫に浮気された主婦が相手の女性のところに乗り込んでいき、その女性の愛人である男性と関係を持ってしまうとか。(笑)
『婦人公論』には小説以外に、エッセイや実際に起きた事件についての考察なども書いています。特筆すべきは、自身の学歴コンプレックスなど、心情を吐露するようなエッセイを書いている点です。
先進的な女性読者の多い『婦人公論』なら、社会的な問題に対する興味を盛り込むことができると考えていたのではないでしょうか。読者に対して、母親に甘えるような気持ちもあったかもしれません。