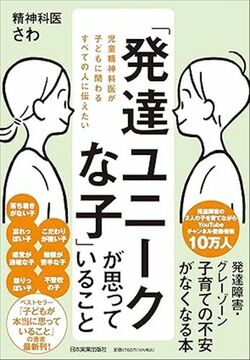おだやかに対話をして、自制心を養う練習
それでも、やはり子どもが怒ってしまうことはあります。
大人だって感情のコントロールが難しいときってありますよね。子どもにはなおさら、常に冷静でいることを求めるのは難しいものです。
大切なのは、その怒りの背景に目を向けることです。
子どもが少し落ち着いたあとに、「さっきはどうして怒ったのかな?」「なにかいやなことがあった?」などと気持ちを少しずつ言葉にしていく練習をするのです。
その際も、子どもが騒いだことを責めるのではなく、「どうしたらよかったか?」を問いかけて、じっくり話を聞く姿勢を忘れずに。
たとえば、子どもが癇癪を起こしたときは、しばらくしてから「さっきは、どういう気持ちだったのかな? どうしたらよかったと思う? お母さんにもなにかできることはあったかな?」などと、おだやかに対話できるといいですよね(「言うは易し行うは難し」と思った方も多いかもしれません。私も自分自身が完ぺきにできているという前提でこれを書いているわけではありませんので、そこはご安心くださいね)。
わが家の長女も小さいころ、癇癪の頻度がとても多く、思うようにいかないときは所構わず床にふんぞり返って泣き叫んでいました。
それが屋外であったときは、他人の目が気になって背中を丸め、泣き叫ぶ娘を抱きかかえて、逃げるように車に戻り、気づくと私の頬にも涙が伝っていました。
車のなかに入ったら入ったで、鼓膜がやぶれるんじゃないかと思うほどの娘の叫び声に、思わず私も「いいかげんにして!!」と声を荒げてしまったこともありました。
そのときの、自分の胸が張り裂けそうになったり、自分の育児を責められているような感覚は今思い返しても大変だったなと思います。
しかし、子どもも親も成長とともに、おだやかなときに少しずつ対話で振り返る。それを繰り返すことで、子ども自身が自分の感情を少しずつ言語化していけるようになっていきます。
すると、怒りに変わる前に自分の気持ちを理解して、感情をコントロールする力も少しずつ育っていきます。