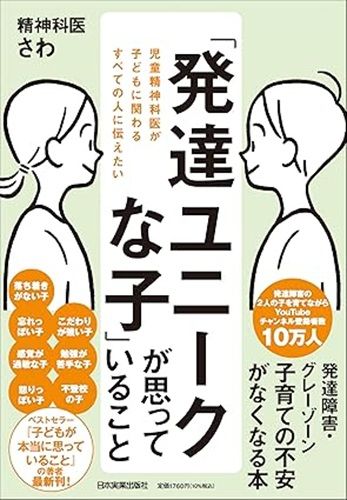トラブルを起こす子ども自身も困っている
ADHDのなかでも多動・衝動性の強い子の場合は、「自分にブレーキをかけられず、突発的に行動してしまう」「相手を傷つけるつもりはないのに、自分の感情や行動がおさえられない」などの特性があって、トラブルになってしまうこともあります。
授業を混乱させたり友だちとけんかになったりして、学校で怒られることもあります。
でも、それらは必ずしも混乱させようとか、人を傷つけようなどと思ってやっていることではありません。子ども自身もどうしたらいいかわからずに困っていることも多いのです。
まず、「本人の努力が足りない」「我慢が足りない」という精神論のようなものはまったく通用しないことを知っておいてほしいです。
前頭前野(ブレーキ役)より扁桃体(危険を察知する“火災報知器”)が優位になりやすく、理性より先に「闘う・逃げる」という反応が出てしまう──そんな脳の配線のちがいが背景にあります。
もともと脳の特性的にその状態になっているのです。言うなれば、「トイレに行きたい」と言う子に、ただ「行くのを我慢しなさい」と言うようなものです。その「トイレに行きたい」が自分ではコントロールしにくい感情の表現かもしれないのです。
わりと我慢できる子もいれば、少しだけなら我慢できる子もいますし、もう限界という子もいます。それに対して「なぜ我慢できないのか」と怒るのは不合理でしかありません。
特性上、我慢ができないということを、知っておくことだけでも対応が変わります。
癇癪は叱るより“通訳”――気持ちを言葉に置き換える手伝いを
※本稿は、『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』(日本実業出版社)の一部を再編集したものです。
『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』(著:精神科医さわ/日本実業出版社)
すべての人が「その人にしかない発達の過程」を持っており、発達とはだれにとってもユニークなものなのです。
実際、診断がつかない子どもたちのなかにも、日々の生活や学校のなかで「困りごと」を感じている子は少なくありません。
「病名がないから大丈夫」ではなく、「困っているなら支援が必要」という考え方が、もっと社会のなかに広がっていってほしい──そう思って、この本を書きました。