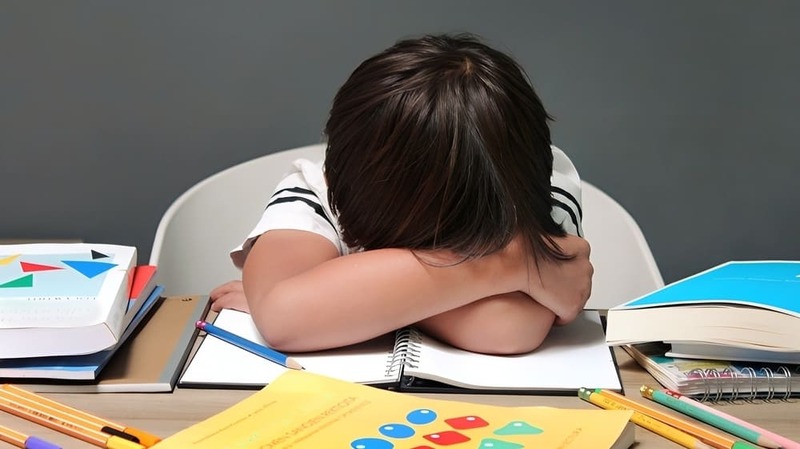現代社会では、子どもたちの発達について、「発達障害(神経発達症)」「定型発達」「グレーゾーン」など、さまざまな分類がされています。そのようななか、「診断名にとらわれることなく『すべての人には、それぞれの発達のユニークさがある』という視点を広げていきたい」と話すのは、5歳以上から大人までを対象にした塩釜口こころクリニック院長・精神科医さわ先生です。そこで今回は、精神科医さわ先生の著書『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』から一部を抜粋して、「発達ユニーク」な子どもたちが感じていることをご紹介します。
なにかが視界に入ると、そっちが気になってしかたがないんだ
子どもの困りごと
じっとしていられない、衝動的に動く、話を聞けない
じっとしていられない、衝動的に動く、話を聞けない
目に入ると「つい」してしまう
多動性や衝動性という特性を持つお子さんの場合、目の前のことが気になってしまうと、つい、あと先を考えずに行動してしまうことがあります。
そのため、教室で落ち着いて座っているのが難しかったり、順番を待つことができずにトラブルになってしまったり、先生が話しているのに話し出してしまう子もいます。
こうした行動が続くと、学校の先生から「いつも問題を起こす子」という目で見られてしまい、よく怒られるという子もいます。
あるお母さんは、毎日のように学校から「今日もトラブルがありました」という電話がかかってきて、そのたびに疲弊してしまうと話していました。
しかし、こうした行動は脳の特性によるものですから、学校の先生にも、まずはこの特性について正しく理解していただくことが必要です。
多動性や衝動性の特性を持つ子は、いろいろなものに興味を持ちやすく、目についたものにすぐに手を伸ばしてしまうことも多いです。
たとえば私のクリニックでは、来院者がすぐにわかるように自動ドアに鈴を取りつけているのですが、毎回その鈴を取ってしまう子がいたり、診察室で私が使っているキーボードを触ってくるお子さんもいます。
「目に入ると触りたくなる」のが、その子たちにとっては自然な反応なのですね。
また、集中力が長続きしないという特性もあり、こちらが話しかけても聞いていないように見えることがあります。
このような特性を持つお子さんに対しては、その行動を問題視するのではなく、その背景にある特性を理解して、環境や接し方を工夫してみてほしいのです。