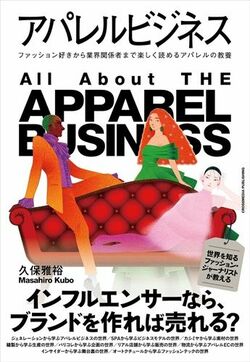「ニューサーティー」のジャンルが確立するまで
話は少し遡りますが、戦前から戦後にかけて、レナウン、三陽商会、オンワード樫山といった、いわゆる大手アパレルといわれる企業が立ち上がり、百貨店を中心にビジネスを広げていきます。
その後1950年代後半から60年代にかけて、アイビールックを日本に持ち込み「メンズファッションの神様」とも称された石津謙介による「VAN」(ヴァンヂャケット)、ゴルフ場やワイナリーまで展開し、ファッションをライフスタイル軸まで広げた先駆者、佐々木忠による「JUN」(ジュン)といったファッションアパレルが成長を遂げます。
60年代になると、小売では鈴屋二代目の鈴木義雄が「SUZUYA」を、市村清がリコー三愛グループの「三愛」など婦人服専門店の大手を誕生させ、やがて全国にチェーン化することでナショナルチェーン専門店が発展していきます。ちなみに「TSUTAYA」を展開するCCC(カルチャーコンビニエンスクラブ)創業者の増田宗昭、ファイブフォックス「コムサデモード」創業者の上田稔男は鈴屋出身、高田賢三は三愛出身など著名人を輩出しています。
また70年代に販売面で協力体制をとった東京ブラウスやグラン山貴などの婦人服アパレルによる連合体「サンディカグループ」という存在も記さない訳にいきません。フランスのサンディカ(パリコレを主催するオートクチュール組合の通称)を使って、日本の専門店向け婦人服アパレルの中核を担おうとします。こういった団塊世代より少し上の人々が作ったアパレルメーカーや専門店に団塊世代が就職し、仕事を覚えていきました。
7~8年も経つと、バリバリと仕事をする自分たちとは少しニュアンスの違うコンサバティブでエレガント過ぎる服に違和感を持ち始め、自分たち30代にとって働きやすく、動きやすい、さらにはあまり女らしさを強調せずとも若々しい団塊世代独自のテイストを確立したくて徐々に独立していきます。
アパレルメーカーは原宿を中心にマンションの一室で始める、いわゆる「マンションメーカー」が誕生し、大手チェーン専門店から独立して、同世代のマンションメーカーから仕入れる地方の個店型品揃え専門店が生まれ、その塊が「ニューサーティー」(新しい30代のための服)というジャンルとして確立します。