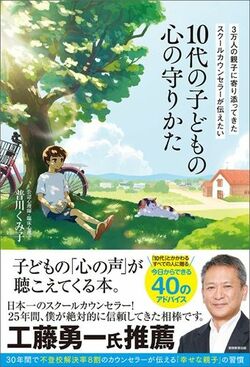子どもが話さないのは、信頼している証かもしれない
大切なのは、子どもの部屋や心のスペースに無理に踏み込まないことです。
とくに思春期以降の子どもは、自分の部屋の空間や感情を大切にするようになり、家族であっても容易には立ち入らせないようになります。しかし、そこで過度に干渉すると、精神的な成熟を妨げることになりかねません。
もちろん、親として心配になるのは当然ですが、その思いを強く押し付けないことが大切です。
子どもが不登校になっていると、「勉強についていけなくなるのでは」「留年したらどうしよう」などと不安になり、その思いを子どもに伝えてしまうこともあるでしょう。そうすることで子どもが危機感を持ち、学校に行くようになるかもしれない、という期待もあると思います。
しかし、子どもはそうした未来の心配を先取りされると、意気消沈してしまいます。「そんなに心配だらけの未来が待っているのなら、もう手遅れだ」と感じ、何もかも放棄したくなることもあります。
不登校の子どもはただでさえ、未来に不安を抱いています。ですから、その不安を助長する言葉は控えた方が賢明です。