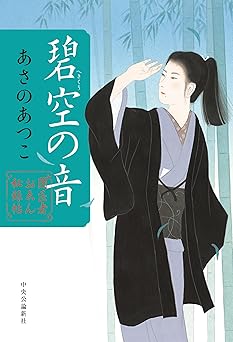二
おゑんが廊下に出るのを待っていたかのように、日が翳った。
空に広がった薄雲がくっつき合い重なり合って、陽の光を遮ったのだ。とたん、風が勢いと冷えを増す。雪女の指先がすっと首筋を撫でて通った。そんな覚えに見舞われる。
風邪を引く前に、手拭いでも巻くかねえ。
首に手をやり、独り呟く。
日は翳ったままだ。雲はさらに厚みを加え。空の青を呑み込もうとしている。
なるほど、末音の見立て通りだ。これは嵐になるね。
植込みの陰から人影が現れた。おゑんを認めたのか、一瞬、足を止める。おゑんは影に向き合うために、僅かに身体を回した。
影が動き出す。
「これはこれは、ずい分とお久しぶりじゃありませんか、甲三郎(こうざぶろう)さん」
「へえ、ご無沙汰しておりやした」
甲三郎がひょいと頭を下げる。何気ない仕草だけれど、若さとしなやかさが存分に匂う。この若さでこの男は、新吉原(しんよしわら)の首代(くびだい)を束ねる。吉原惣名主(そうなぬし)の命(めい)であれば、他人を葬るのはむろん、己自身を己で始末しさえする。首代とはそういう男たちだった。
尋常な者が近づく相手ではないし、尋常に生きていれば接することは、ほぼない輩だ。そんな首代と親しげに挨拶を交わす自分も、尋常の枠を跨ぎ越している――と、思う。それはそれでいい。枠とは中に鎮座するためのものでは、ない。囲われて平穏を味わうためのものでもない。少なくとも、おゑんにとっては邪魔でしかなかった。だから、跨ぎ越し、押し破り、砕き、外に出る。
枠の外には、こういう男が生きている。厄介でもあり、とてつもなく剣呑でもあるけれど、おもしろい。興をそそられるのだ。だから、きっぱりと背を向けて、遠ざかれずにいる。そんな己の心の有り様に、おゑんは戸惑いもするし、嗤(わら)いたくもなる。眉を顰めたくもなる。
おまえは、本当に愚かだねえ。わざわざ、危なっかしい道を選ぶのかい。
わかっている。避けられるのならば避けて通らねばならない相手だ。何が潜んでいるかわからない獣道をわざわざ選ぶほど、向こう見ずでも馬鹿でもないつもりだ。けれど、つもりはつもりでしかない。今も、身構えながら口元を綻ばしていた。
「座敷に上がられますか。今日は、末音もお春さんもおりますよ。先日も、お春さん、甲三郎さんのことを案じてたんですよ。『ちゃんと食事をしてるのかしら』ってね。ふふ、弟を案じる姉さまの口調でしたね」
嘘ではない。お上手でもない。この若者の歓心を買う要をおゑんは一分も感じていなかった。口先だけの綺麗事が通用するとも感じていない。
お春は、もう何年もおゑんの助手(すけて)を務めていて、長い間ではないが、甲三郎と共にここで暮らした経緯(いきさつ)がある。「何だか妙に気になるお方ですよね。強いのか脆いのか、よくわからなくて。この世の大半のことを知っているようにも、ひどく初心(うぶ)なようにも見えてね。ちょっと、ハラハラしたりするんです」というのが、お春の目に映った甲三郎の姿らしい。お春は、この後、ちらりとおゑんを見上げ、口元に笑みを浮かべた。
「そういうところ。おゑんさんに似ていますよね」
「あたしに?」
「ええ、似てますよ。あたし、おゑんさんにもハラハラしますもの。それなのに、誰よりも頼りにしているし、寄り掛かってもいますものね」
「お春さんに頼られてるとは気が付かなかったね。そりゃあ、身に余る誉(ほまれ)じゃないか」
「まっ、おゑんさんたら、そうやって、すぐにからかうんだから」
「からかっちゃいませんよ。本音です、本音。お春さん、このごろちょいとばかり疑(うたぐ)り深くなってないかい」
「え、そうですか。嫌だわ、歳のせいかしら。気を付けなくっちゃ」
そんな、戯れに近いやりとりを交わした。おゑんにしてみれば、寄り掛かっているのはこちらだろうという思いがある。お春は文字通り、八面六臂の働きをしてくれていた。おゑんの助手をしながら、赤ん坊たちを育てながら、ときに台所に立ち、患者たちの世話もする。何人か手伝いの女を雇ってはいるが、お春がいなければ、どうにもならない。よく、わかっていた。ありがたいと心内で手を合わせることは、数限りなくあった。
そのお春が甲三郎を気に掛けている。
まともなものを食べているか。
十分に眠っているか。
無茶をしていないか。無理をしていないか。
お春は小娘ではない。生きるに長けた三十路(みそじ)の女だ。世間の惨(むご)さも温もりも、人の世の仕組みも十分に心得ている。だから、吉原の首代がどういうものか知らないはずがない。知った上で、案じているのだ。
姉が弟を案じるように。
それを甲三郎が喜ぶのか、面倒なだけだと振り払うのか、何とも感じないのか。おゑんはまだ、掴んでいない。掴もうともしていない。ただ、おまえさんの身を案じている者がいるのだと、それだけは伝えておこうと思う。
「先生は、どうなんでやす」
「え?」
甲三郎がなにを問うたのか、わからない。おゑんは首を傾げた。
「先生は、あっしのこと、ちっとは思い出してくれやしたか」
そう口にしてから、甲三郎は心持ち上体を引いた。自分の言葉に驚いているのだ。よく日に焼けた顔が赤くなる。
「あ……す、すいやせん。いや、その冗談です。はは、ほんとにつまんねえ冗談を言っちまった。聞き流してくだせえ」
「今、思いましたねえ」
「へ? 今って……」
「甲三郎さんの顔を見たとたん、ふっと思いましたよ。このお人は、会わなかった間、どうしていたんだろう、とね」
「はあ……そうでやすか。じゃあ、顔を見るまでは思い出しもしなかったって、こってすね」
甲三郎の口調は拗ねた童のようでもあり、落胆した隠居のようでもあった。
つい、笑ってしまう。
「そんなこと、ありませんよ。お春さんと甲三郎さんの話を何度かしたんですから。ただ、あたしの性分でね。過ぎた日々をあれこれ思い返すのは好きじゃないんですよ」
「えっ、あの……先生の中で、あっしは既に過去の者になってんでやすか」
「まっ、もう甲三郎さんたら」
堪えきれなくて、吹き出していた。
(この章、続く)