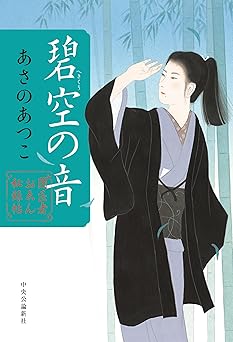四
その茶屋には暖簾(のれん)も看板も出ていなかった。
路地の奥にあり、弁柄の格子戸、その紅色だけが仕舞屋(しもたや)にはない艶な気配を漂わせている。
「おじゃましますよ」
平左衛門が格子戸を開ける。
その向こうは意外にも、小さな庭になっていた。泉水や築山はなかったが、白い砂利が敷き詰められ、苔むした大小の石が点々と置かれていた。白い湖面に浮かぶ小島を模しているのだろうか。
やはり、弁柄の格子窓の付いた平屋が建っていた。
「まあ、平佐衛門さん、おいでなさいまし」
平屋の中から女が出てくる。
四十はとっくに超えているだろう。鬢(びん)にも髷にも白いものが目立つ。笑んだ目元と口元には細かな皺が寄り、首にも筋が浮き出ていた。
それでも美しい女だ。
なぜ、美しいのか。おゑんは束の間思いを巡らせ、すぐに答えを掴んだ。
女は姿形ではなく、立居振舞が美しいのだ。だらりと緩んでも、ひどく張り詰めてもいない。柔らかく、けれど、崩れのない仕草を保っている。
素人じゃないね。さて、どんな来し方があるのやら。
庭に面した小座敷に案内されながら、思う。
もっとも、吉原に住まう女だ。容易く語れるような過去を背負ってはいまい。
「でも、珍しゅうございますよねえ。平左衛門さんが女の方をお連れになるのは」
「ああ、そうかねえ。けれど、この方は並の女子(おなご)とは違うのさ」
女は足を止め、おゑんに顔を向ける。微かな笑みが浮かんでいた。
「もしかして、おゑん先生ですか。お医者さまの?」
おゑんは軽く頭を下げた。
「はい。ゑんと申します。お見知りおきを」
「この茶屋の主、イノでございます。お目にかかれて嬉しゅうございますよ、先生。ささっ、どうぞ、お上がりくださいな」
沓脱(くつぬ)ぎ石から廊下に上がる。その先の小座敷は畳替えを済ませたばかりなのか、藺草(いぐさ)の清々とした香りに包まれていた。
「平左衛門さん、いつものお飲み物でよろしいですか」
「ああ、頼む」
おイノは僅かに腰を屈め、去って行った。
「ここは上座も下座もございません。先生、お好きなところにお座りください」
「ありがとうございます。では、あたしはここで」
庭に向かって開け放たれた障子戸、その近くに腰を下ろす。平左衛門が苦笑した。
「相変わらず、その場所を選ばれますか」
「ええ、お庭が美しいもので。ゆっくり眺めながらお茶をいただきたく、思いましてねえ」
「この庭が気に入りましたかな」
おゑんの正面に座り、平左衛門は優しげな笑みを浮かべる。むろん、そう見えるだけだ。吉原の惣名主の為人(ひととなり)に優しさや慈悲心が欠片もないとは思わない。むしろ、人並み以上に宿しているのではないか。ただ、その情を抑え込み、吉原の則や掟を何よりも重んじる。そのために、誰の命が危うくなろうと一顧だにしない。そういう力業ができる男だ。できねば、務まらぬ役をずっと担っている。
だから迂闊に踏み込まない。能う限り、離れている。それくらいの用心はしていた。それでも、こうして、隠れ屋のような茶屋で向かい合う羽目になる。
おゑんは小さな庭に目をやった。
白い砂利が昼下がりの陽の光を浴び、淡く輝いていた。雀が一羽、舞い下りて、砂利の間をついばんでいる。その雀の羽も淡い光を浴びて、艶やかだった。
「美しいお庭でござんすね」
「ええ、わたしもこの眺めが好きで、時折、寄るのですよ」
「足音が響きますものね」
「は?」
「これほど砂利を敷き詰めていると、どれほど気を付けても、身が軽くとも、足音を立てずに渡るというのは、無理でしょう」
おゑんは平左衛門に笑みを返した。
「よい盗人(ぬすっと)止めになりますね。外に潜んで盗み聞きするのも難しいでしょうし。うちも、真似てみようかと考えておりました」
平左衛門が僅かに顎を引く。笑みは消さない。
「なるほど、密談するにはうってつけの場所だと、そう仰いますか」
「密談? いいえ、そんな滅相もない。惣名主なら、密談に相応しい場所など十も百も知っておられるんじゃござんせんか。こんな、穏やかで美しいところを、そんな野暮な用に使うとは思えませんけれど」
はは、と平左衛門が笑い声を上げた。
「先生、わたしを掣肘(せいちゅう)しておられるのですか。密談など遠慮申し上げる、と」
「まあ、そのように受け取られましたか。あたしは、美しいものを美しいと口にしただけのつもりでした。他意はございませんでしたがねえ」
平左衛門が再び、笑う。今度は作り物ではない、弾む声だった。
膳を手にしたおイノと小女が入ってくる。
「おやまあ、平左衛門さんがこんなに楽しそうに笑うなんて。お付き合いもずい分と長くなりますが、いつ以来でしょうか。初めてかもしれませんねえ。驚いたわ」
口先だけでなく本当に驚いているらしく、おイノの目元は引き締まっていた。その表情のまま、おゑんの前に膳を置く。平左衛門の前には小女が同じ膳を運んだ。
「え、これは……」
膳の上には、小魚の甘露煮の鉢と漬物の皿が載っていた。それらは、おゑんには馴染みの料理だ。けれど……。玻璃の器に赤紫の飲み物が入っている。器は卵を細長く伸ばし半分にしたような形をしていた。細い脚が付いている。
「珍陀酒と申します」
おイノが囁くように教えてくれた。
「ちんたしゅ、ですか」
初めて聞く名前だ。
「はい。珍しいに阿弥陀(あみだ)さまの陀、それに酒と書きます。異国のお酒だそうですよ。平左衛門さんがお好きで、ぜひ先生にも味わっていただきたいと仰るのです。どうぞ、ご賞味くださいな。付け合わせは、わたしの手料理です。このお酒にはこってりしたものが案外、向いておりますの。先生のお口に合うとよろしいのですが」
平左衛門をちらりと見やり、おゑんに一礼すると、おイノと小女は座敷を出て行った。
「珍陀酒……ですか。これはまた、滅多に味わえないお酒でござんすね」
「ええ、そうだと思います。おイノは異国の品を扱う商人の女房でしてな。いや、その男はとっくに亡くなったのですが、その伝手(つて)で今でも、なかなかに珍しいものを手に入れ、こうして楽しませてくれるのですよ」
「そうですか。きっと、店を切り盛りするのに長けたお内儀(かみ)さんだったのでしょうね。惣名主とは、そのころからのお知り合いなのですか」
「そのずっと前からです。夫婦(めおと)だったころを入れると、はてさて、もう三十年近い付き合いになりますかねえ。月日の経つのは早いものですな」
息が詰まりそうになる。器に伸ばしかけていた手が止まり、つい、目の前の老人を凝視してしまった。ほんの束の間のことだが。
「ははは、驚かれましたかな」
「ええ、かなり。心の臓が止まるかと思いましたよ」
「心の臓が止まるほど先生を驚かせた? これは、また、おイノの手柄だな。大手柄だ」
「何を言ってるんです。あたしは、これでも気が小さいんですよ。しょっちゅう驚いちゃ、粗忽(そこつ)な真似をして、周りに呆れられたりしてます」
嘘ではない。自分は気が小さく、臆病だ。だから用心するし、気を配る。患者の容体も含め、都合のいい思い込みをしない。いつも、最も悪い有り様を心に留めておく。そういう生き方をしてきた。
(この章、続く)