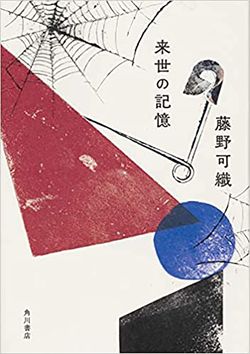
わたしたちの似姿のような登場人物たち
藤野可織は、今ここにある世界と地続きでつながっているのに、凡庸なわたしには見えないだけなのかもしれない異世界を垣間見せてくれる作家だ。その魅力を堪能できるのが、最新短篇集『来世の記憶』なのである。
前世おっさんだったことを覚えている女の子。豚肉みたいに腐ったりしないように、お母さんみたいに劣化したりしないように冷蔵庫で寝るようになった少女。蒐集した切手で占いをすることに夢中になって、男の子たちを眼中から排除してしまった女子高生ら。人々が茹で上がったスパゲティの束と化して死ぬ奇病が蔓延している世界で、スパゲティを食べることがやめられない〈ぼく〉。19世紀中頃に考案された〈鳥かごのような、牢獄のような美しい下着〉を血肉化することで、女性器を男どもから取り戻した女たち。会社で雇っている簡易医療用AIのニコラス・ケイジと語らう女子社員。怪獣を虐待するために、凶器を持って森に入っていく女たち。自分だけの最高のかばんを手に入れて、何処かへと旅だっていく非正規雇用の女性たち。
などなど、収録20篇に登場する人物たちは一見突飛なようだが、説明を極力抑えながらも「ここしかない!」という適切な箇所にカチリとはまるピースのように的確な語り口によって、地に足をつけた存在感を獲得し、わたしたちの似姿のように思えてくる。
たとえば、とても短い物語「眠るまで」の〈私〉。夜なんとなくネットで死体の画像を眺めている彼女が抱えている、働いている今も、大学でも、高校でも、そのさらにずっと前から日常をこなしてきたというけだるい諦念は、多くの人に覚えがあるのではないだろうか。しかし、それを死体の画像を見るというあまり普通ではない行為に接続することで、倦怠感はより異様な迫力をもって、わたしたちの胸元に突きつけられるのだ。
〈みんな、私のために、いちいちなにかを思ったりしない。そこまで私のことを気にかけてなどいない。だからだいじょうぶ。すぐに明日になる。今日は追いやられ、押し流され、記憶のなかでほかの日々に均(なら)され、同化していく〉、そんな日常の果てに死体として在る自分を想像して、わたしたち読者はぞっとしてしまうのだ。
ヘンテコなのに普遍的。それが、藤野マジックの真骨頂なのである。







