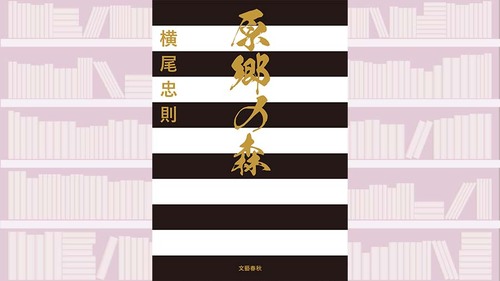
芸術家たちの思いが聞ける不思議な場所――
横尾忠則さんといえば、Y字路の画が浮かぶ。建物を挟んで二つに分かれた道は、よくある景色、あるいは人生の道を思わせる。
本書でYと呼ばれる主人公の〈俺〉は横尾さん自身だろう。いわゆる小説といわれるものとはずいぶん形が違う。何しろ登場人物が多く、実在した人もいればフィクションの人物もいる。
「原郷の森」とは、著者だけが知る場所。この世に生まれた人間の魂の故郷みたいな場所――まるで夢の中のよう。ここに現れる〈俺〉以外の人はこの世のものではない。
普通、夢は見たいと願っても見られるものじゃない。ところが原郷の森は著者が願えば行ける場所で、著者はあらゆる霊界の死者たちと交流。芸術家たちに、生前に達せられなかった思いを語らせる。最初に出てくるのは三島由紀夫。評伝小説とも歴史小説とも違う三島の造形は、語り口が聞こえてきそうなほどリアルに迫る。
ほかに登場する人たちを少し羅列してみると、マルセル・デュシャン、谷崎潤一郎、永井荷風、ピカソ、熊谷守一、井上光晴、織田作之助……時空を超えてどこからともなく集まってくる。原郷の森はどんどん賑やかになる。
モネ「見るということは意識である。それを写すことによって絵が生まれていく」運慶「凄いだろうと驚かすことが仏像の存在だ」
シェイクスピア「美しいことを描くということは、その三倍位の醜い世界を知らなければ描けない」
俺「芸術はやはりどこか時代とズレていなければ駄目だと思う」
芸術家の丁々発止のやり取りを客席から観るかのよう。それぞれの言葉から浮かび上がるのは芸術とは何か、ということ。古今東西の芸術家の言葉の海に浸れば、身の回りにある作品への見方が変わりそうだ。







