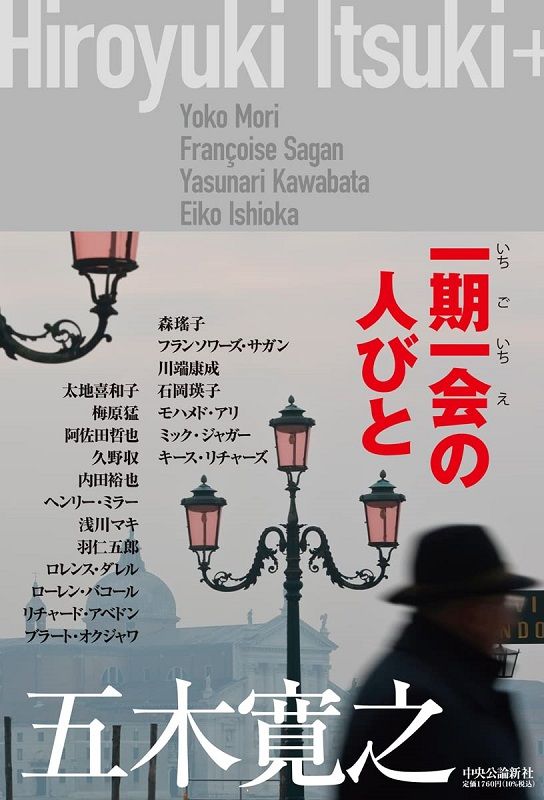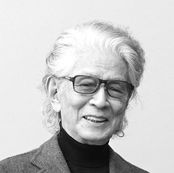モノも捨てる、記憶も捨てる、人も捨てる。
僕は「捨てる」ことに反対しているわけではありません。ただモノをどんどん目の前から消して生活空間をスッキリ整えたとして、それで幸せなのか、と問いたい。モノを手放すのは、自分が過ごしてきた時代の記憶、歴史を忘れていくのと同じであるように思える。
今、ヨーロッパではウクライナとロシアが戦争をしています。大量生産・大量消費を前提にした資本主義のサイクルの中で最大の「廃棄」は戦争です。今回のウクライナの戦争は、滞貨一掃という問題をはらんでいることも忘れてはいけません。
同時に戦争は世界的な難民問題も引き起こします。難民というのは住んでいたところを離れざるをえなかった人たちであり、国を捨てさせられた人たちでもある。思想とか信念といったものをひっくるめて無理やり手放させられる、現代の悲劇です。
僕自身、前述したように、終戦後「棄民」になりました。国から「棄てられた」経験をしたのです。「捨てる」という行為を突き詰めると、こういうところまでいってしまう。
産業界に目を向けると、ファッション業界では大量の衣料品が廃棄されていることが問題になっている。食品業界でもフードロスに対する取り組みを多くの企業が行っています。
この問題は、まさしくいまの課題です。作っては廃棄するこれまでのやり方では限界が来ている。今世紀最大の課題は「捨てない」ことなのでしょう。
****
現在を豊かに生きるためには、未来への展望を持つと同時に、過去の記憶が現在をしっかり支えている状態でないといけません。そうでないと、薄っぺらな人間になってしまう。「捨てない生き方」は、過去の記憶とともに生きるということです。
記憶のよすがになるガラクタが身の回りにたくさんあれば、後半生は豊かな「回想」を楽しめる黄金の時代になるのではないでしょうか。