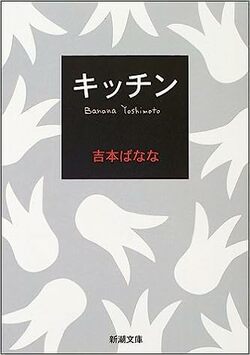私はずっと、泣きたかった
物語序盤、みかげの元をある男性が訪れる。名前は、田辺雄一。亡き祖母の行きつけの花屋でバイトをする彼は、みかげの祖母と親しかった。そんな雄一が、みかげに「しばらくうちに来ませんか」と提案する。直感的な本能で雄一を「信用できる」と判断したみかげは、後日彼の家を訪ねた。以降、雄一と、雄一の母親・えり子、みかげの3人による不思議な同居生活がはじまる。
この3人は、世間一般から見れば少し変わっている。だが、多数決でいうところの少数派であるというだけで、人を傷つけるわけでもなければ貶めるわけでもない。むしろ彼らは、大切な人をちゃんと大切にしようと心がける人たちだった。遠くの他人には立派な態度で接するのに、身近な人間を粗末に扱う人は存外多い。だから、母親のえり子さんを大事にする雄一が、雄一を大事にするえり子さんが、そんな二人を大事にするみかげが、私は好きだった。
「自立して早く田辺家を出なくては」と焦るみかげに、えり子さんは言う。
“「よくね、こういうこと言って本当は違うこと考えてる人たくさんいるけど、本当に好きなだけここにいてね。あなたがいい子だって信じてるから、あたしは心から嬉しいのよ。行く所がないのは、傷ついてる時にはきついことよ。どうか、安心して利用してちょうだい。ね?」”
行く所がないのは、傷ついてる時にはきついことよ。
そうなんだよ、と心で呟いた。同時に、ぼたぼたと瞳から水分がこぼれた。それは「涙」なんていうかわいらしいものではなく、まさに「体液」と呼ぶにふさわしいほどの迫力で私の頬を流れ落ちた。どんなに傷ついても、逃げ場所がない。それは、とても苦しくて、きつくて、寂しくて、孤独だった。
みかげは祖母を亡くしてから、すぐには泣けなかった。人は、悲しい時、辛い時にすぐさま涙が出るとは限らない。痛みが大き過ぎると、逆に泣けないこともある。
両親に愛されたかった。普通がよかった。幼馴染に側にいてほしかった。大学に行きたかった。文学を勉強したかった。せめて高校は卒業したかった。
どうして私は、そういうものを何ひとつ持っていなくて、みんなが当然のように着こなしている常識さえもわからなくて、お風呂で独りで本を読んでバカみたいに泣いているんだろう。
そう思いながら、泣いた。でも、そんな私の隣に、みかげと雄一とえり子さんがいた。本の登場人物は、親友にも戦友にもなり得る。彼らに会いたければ、本を開けばいい。それだけで、孤独の何割かは埋められる。
寂しい時に温かい物語を読むと、身も蓋もなく泣いてしまう。人前では滅多に出ない涙は、一人になった途端、歯止めが効かなくなる。だから、頁をめくる手を止めなかった。私は、ずっと泣きたかった。弱みを見せても誰にも付け込まれない場所で、好きなだけ泣きたかった。体を売った夜も、「可哀想な子だ」と蔑まれた日もこぼさなかった涙が、まとめて湯船に落ちた。