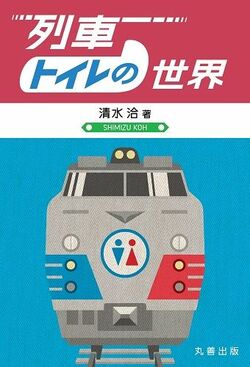当時はメーカーの関心も高かった
同年に新幹線車両のトイレはタンク式に決定しました。一方、在来線の車両は便所の位置がばらばらのため汚物の回収が困難となり、当面はタンク式の採用を見合わせていました。また、タンク式を採用した新幹線でも汚物を1往復毎に車両基地に入区することが車両運用上のネックになっていました。
1964(昭和39)年度より直接汚物を粉砕・消毒して垂れ流す「浄化式」と汚物をタンクに溜め込み、洗浄水は繰り返し利用する「循環式(鉄道車両金具製造、五光製作所)」の比較研究が開始されました。
1967(昭和42)年10月より順次、循環式への改造が開始されました。1969(昭和44)年度中には新幹線はすべて循環式に改良されましたが、循環式の実用化には多少時間が必要なため、在来線車両には粉砕式を継続して取り付けることになりました。
粉砕式の改良点は、点検蓋の設置、飛散防止覆いの取り付け、異物取り出し装置の取り付け、タンクの大型化、また寒冷地用としてヒーターの設置などが実施されました。
一方、在来線車両の循環式への改造は、予算という壁にぶつかっていました。