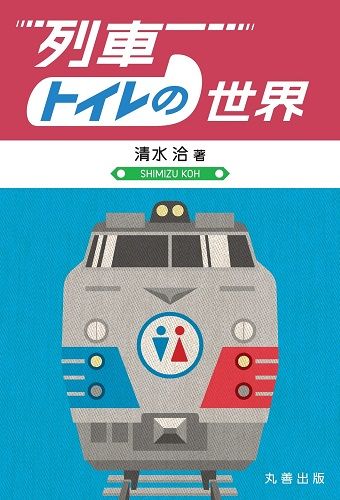循環式から真空式へ
国鉄の民営化により車両からの汚物垂れ流し対策はJR各社が引き継ぎましたが、その主流は循環式(図1)でした。
1989(平成元)年、国鉄の民営化後初めて「列車用個室便洗ユニットシステム」が寝台特急「北斗星」や「トワイライトエクスプレス」に常備されました。
一方、航空機では水洗用の水を極力少なくする真空式のトイレが主流ですが、列車のように振動がある車両には不向きと言われていました。
1993(平成5)年JR九州の車両に日本で初めて真空式トイレユニットシステムの試験が始まりました。その結果、JR九州特急「つばめ」(787系電車)の量産型車両に真空式トイレユニットが取り付けられました。
1994(平成6)年にはJR北海道の新型振り子式特急気動車281系(スーパー北斗)に「真空ブロワートイレシステム」が常備され、翌年にはJR西日本の新幹線500系車両に真空式トイレユニットが採用されました。
1996(平成8)年にJR東海、JR西日本の東海道・山陽新幹線700系車両に真空式トイレユニットが採用され、日本の列車トイレは真空式トイレが主流となりました。
現状、日本では垂れ流しの車両は1両もなく、汚物はすべてタンクに貯留されて車両基地で処理されるか、下水放流で処理されています。
※本稿は、『列車トイレの世界』(丸善出版)の一部を再編集したものです。
『列車トイレの世界』(著:清水洽/丸善出版)
快適に移動できるのは、列車トイレの発達あってこそ!
糞尿がレールに飛び散っていた「垂れ流しトイレ」の時代。現在の綺麗で快適なトイレに至るまでは技術者の地道な努力の積み重ねがあり、それにより日本は世界に先駆けて垂れ流しトイレの全廃を実現した。しかし、海外の列車に目を向けると今でも垂れ流しトイレが残っている。 日本における列車トイレの歴史、汚物の処理方法、さらに海外の列車トイレの紹介を通して、列車の快適性を支える「列車トイレ」から日本そして海外の衛生環境を考える一冊。