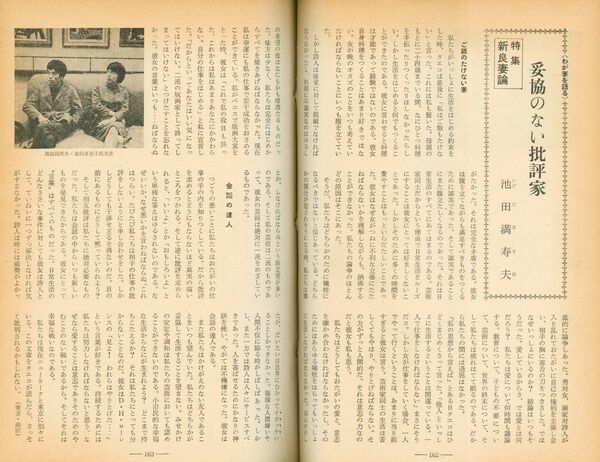タエコとマスオ
「婦人公論」1966年10月号の特集「新良妻論/新しい結婚の生態」に、池田満寿夫が草月流の創始者・勅使河原蒼風らと並び寄稿している。題は「妥協のない批評家」。池田が指す妻とは、富岡多惠子のことである。ここではタエコとなっており、タエコとマスオが詩人と版画家の互いの呼び方であった。
6年前、駆け落ちして暮らしはじめたとき、24歳のタエコはご飯も炊けなかった。それなのに、生活をはじめるとなんでも作ることができた。けれど、だ。
〈女が晩のオカズのことをいつも考えていなければならないことにいつも腹を立てていた〉〈芸術家同士だからという理由で日常生活をルーズにすることは彼女にとっては好ましくないことであった。しかしそのために多くの時間を費やすことはもっといらだたしいことであった。彼女はなぜ女がつねに不利な立場にたたねばならないかを理解しながらも、納得することができなかった。私たちの論争のほとんどの原因はそこにあった〉〈私たちはどちらかのために犠牲になるべきではないと信じあっている〉〈相互批評は私たちに絶対必要なものだった。私たちは会話の中からいつも新しいものを発見できたからである〉
敗戦時、富岡は小学4年で、満洲からようよう引き揚げてきた池田は6年生。戦後民主主義の男女平等教育を受けたふたりは、芸術論から生活の細部に至るまで、あらゆることを疲れ果てて眠るまで議論しあうのが常だった。
この年の6月、池田は、かつて棟方志功が受賞した、版画では世界最高峰のヴェネチア・ビエンナーレの国際版画部門で大賞を受賞した。池田の世界的評価が決定したと知った夜、ローマの街を歩きながら、タエコはマスオに告げたという。
〈彼女は「これで私の役目も終った。これからは私はあまりあなたにかかわらない。自分の仕事をはじめる」と私に宣言した〉
池田がニューヨークで書いた「新良妻論」が読者の目に触れるひと月前、日本にいた富岡は「文藝」9月号に、詩「ニューヨークではなにもすることがない」を発表する。
タエコがニューヨークでしていたことはなにか。マスオの通訳、画廊や美術館へのガイド役に、彼のために英語の手紙を読み、その返事をタイプで打ち、ワークショップを借りてやったエッチングの制作では用紙の水張りやその取り出し作業までと、読売新聞の美術記者だった田中穣が記している。
〈亭主の仕事にかかわりを持つ限り、彼女は一冊の本すら読めず、彼女にとっても一生を賭けた仕事であるはずの詩の一行にさえ、思いめぐらすことはできなかった〉(「小説・池田満寿夫」『池田満寿夫20年の全貌』1977年刊)
翌67年のお正月、池田に執筆を依頼した「婦人公論」の編集者、田中耕平のもとには池田満寿夫・富岡多惠子連名で版画家の手による羊の賀状が届いた。前年7月の富岡の帰国から遅れること4カ月、池田も11月に日本に戻っていたのである。だが、3月になると、彼は約1年間のベルリン留学へと旅立ち、タエコとマスオは再び別々の土地で暮らすことになった。
富岡とローマで別れたあと、池田はニューヨークで24歳のリラン・ジーと恋におちていて、ベルリンにはリランを呼び寄せるのだ。だが、この時期の富岡はまだそのことを知らない。