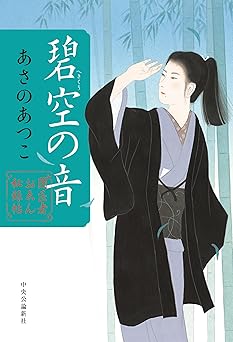「ほんとに、おかしいこと。久しぶりに顔を見せたと思ったら、こんなにも笑わせてくれるなんて、やはり、並じゃありませんねえ」
「いや、別に、先生を笑わせる気はさらさらねえんですが」
風が吹く。首筋が冷えていく。
「先生」
甲三郎が一歩、前に出た。
「今日はこれを預かってきやした」
懐から一通の書状を取り出す。仄かに香が匂った。
「花魁(おいらん)からでやす」
「お小夜(さよ)さんが?」
新吉原江戸町(えどちょう)一丁目美濃屋(みのや)の花魁、安芸(あけい)。今、吉原でただ一人、張見世(はりみせ)をしない呼出し昼三(ちゅうさん)の位を持つ。その花魁の本名が小夜だ。おゑんは乞われて、月に一度か二度、美濃屋の遊女たちを診ていた。美濃屋の主、久五郎(きゅうごろう)は大見世(おおみせ)、総籬(そうまがき)の妓楼の主人にしては小心な、肝が据わらない男ではあるが、女たちを粗略に扱うことはなかった。
身体を壊すほど客を取らせることはなく、まともな食事を 用意し、病に罹れば医者の診療を受けさせる。
遊女屋にとって、女は商売品だ。少しでも高く、長く売るために、美濃屋久五郎は女たちを丁重に扱う。料理屋が味付けを工夫するのと、瀬戸物屋が器を磨くのと、同じだ。とりたてて賞されるものでは、ない。それでも、切見世(きりみせ)の女郎のように働くだけ働かされ、病になれば薬も与えられず放っておかれ、死ねば菰(こも)に巻かれて投込み寺に捨てられる。自分の見世の女たちをそういう目に遭わせないだけ、ましだと割り切らねばなるまい。
吉原は極楽と地獄が背中合わせの場所なのだ。
お小夜は、そういう吉原で二千人とも言われる遊女の頂に立っている。
見事な手跡(て)の文に目を通す。
逢いたいと訴えていた。
先生にお逢いしたくて、たまらぬのですと。
駆け引きはない。古歌をもじった粋な誘いも、美しいけれど空疎な恋の文言もない。ただ一途な想いが吐露されているだけだ。お小夜は、それを隠そうともしていなかった。隠すゆとりさえ、なかったのだろうか。
「甲三郎さん」
「へえ」
「お小夜さんは、息災なのですか。身体を壊しているとかでは、ないですね」
「へえ、病で臥せっているとかじゃありやせん。いつも、堂々として見事な、花魁振りでやす。といっても、傍(はた)から見てのことに過ぎやせんが」
「……そうですか」
吉原は江戸に咲いた徒花(あだばな)だ。厳冬であろうと炎陽であろうと、色褪せも萎(しお)れもせず咲き誇る。花魁はその花の中でひときわ艶やかに、鮮やかに花弁を広げる者だ。大輪の牡丹の妖艶さと百合の清らかさを併せ持ち、一夜草の可憐さと儚さを纏う。
だから人ではない。手を掛け、時を掛け、吉原が生みだした幻だ。
幻は病むことも衰えることも、老いることさえない。病も衰えも老いも許されないのだ。人は幻に現の影も傷も認めない。ただ、幻であることだけをひたすら求める。
けれど、お小夜は生身の女だった。心があり、身体を持ち、泣きも笑いもする。
「で、本当のところどうなんです。傍の人ではなく、甲三郎さんの目から見て、お小夜さんは大丈夫のようですか」
頭上を黒い鳥の影が過った。
何だろうか。雀にしては飛翔が鋭かったし、燕の渡りには早過ぎる。
「ああ、ごめんなさいよ。こんなところで立ち話じゃお粗末過ぎますね」
「いえ、あっしは文を届けに来ただけなんで。けど……できれば、先生のお返事をいただければとは思ってやす」
「お小夜さんが言いましたか」
甲三郎は無言で首を横に振った。
「じゃ、甲三郎さん一人のお考えなんですね」
「……でやす。花魁からはただ、この文を先生に届けて欲しいと頼まれただけでやす。なんで、返事云々についちゃあ、あっしが勝手にお願いしてやす。出過ぎた真似だと、わかっちゃあいるんですが、先生のお顔を見たらつい、口が滑っちまった」
おゑんは空を見上げる。雲の流れが明らかに速くなっている。鳥の影はどこにもない。
「時が惜しいですか」
「はい?」
「末音の見立てによると、嵐が近いようですよ。けれど、荒れるのは夜半になってから、らしいのです。宵までなら、濡れずに吉原に帰れるでしょう。そして、宵までには、もう少しばかり間がある。ありきたりの挨拶で済む話ではなし、ちょいと上がってゆかれませんか。むろん、甲三郎さんの都合がよろしければですが」
促すように、相手を見詰める。
「へい。じゃあ、お言葉に甘えやす」
甲三郎は素直に草鞋を脱いだ。懐から手拭いを取り出し、素早く足裏を拭う。どうということのない所作が滑らかで、美しい。
この男は一瞬の迷いもなく、もたつきもなく、滑らかに刃を振るえるのだろう。草鞋を脱ぐように、手拭いを取り出すように、足裏を拭くように、何の雑作もなく人を殺(や)れる。
寸の間だが、そんな埒もないことを考えた。
「ここは?」
座敷に一歩入るなり、甲三郎は辺りを見回した。
一風変わった一間に見えただろうか。
壁に沿って設えられた棚には、さまざまな陶器や玻璃の瓶、形も大きさもまちまちの木箱、紙箱がきちんと仕舞われている。明かりを取り入れるための窓の横には百味箪笥(ひゃくみだんす)が鎮座し、その上には、大小の薬研が置かれていた。この辺りまでは、甲三郎にとって馴染みとはいかなくても、珍しさに目を見張ることもないだろう。ただし、奥まった一角、末音の仕事場には些か、驚くかもしれない。料亭の調理台に似た台があり、香炉のような器がずらりと並び、薄い煙を立ち上らせているものもあった。
元の姿が思い描けないほど干からびた何かが、天井から幾つもぶら下がっているし、箱の中で折り重なったり、瓶にぎっしり詰められていたりもする。すり鉢だのすりこ木だの、素人には何に使うのか思いもつかぬだろう奇妙な形の道具がやたら目に付くが、散乱しているわけでもなく。それなりに、あるべき場所にあるという感じを強く受ける。
(この章、続く)