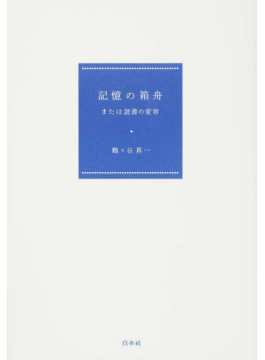記憶の箱舟
または読書の変容
白水社 2800円
大きく変わった「読書」とは
そもそもどんな営みか
インターネットという新しい情報伝達手段が登場し、本を読む人が減ったと言われる。しかし、そもそも読書とはいかなる営みなのか。本書はその変容の来歴を辿ることで、けっして悲観的ではない未来を導き出そうとするエッセイ集である。
まず著者自身のこんな記憶から語り起こされる。1歳か2歳の頃、スイカの切り身の果肉をスプーンですくおうとして失敗し、汁が畳にこぼれてしまった。その記憶から、もう少し大きくなった後に読んだ『クマのプーさん』の絵本の記憶が導かれる。だがそれは偽物で、〈なだらかな緑の丘をプーがなぜかジープに乗ってあらわれる〉のである。
こうした個人史をひもといたのちに、本書は人類の読書史総体を概観していく。中国文明の影響下で始まり、次第に独自の文化を生み出していった日本の読書史と、キリスト教との深い関連のなかで発展してきた西欧の読書史とは、さしあたり別の章で語られる。だがその両者は、その後で検討される「索引」と「記憶術」という二つの補助線によって、一つの大きな「読書」のなかに溶け出していく。
記憶については、ベルクソンが定義した「意志的記憶」と「自発的記憶」いう二つのあり方が紹介される。前者はいわゆる暗記のことだが、後者は冒頭で描かれたスイカと偽の『プーさん』絵本のエピソードのような、連想によってふいに想起されてしまうイメージのことだ。
本の索引はたんなる検索装置ではなく、本と人の記憶とを有機的に結びつける仕組みであり、記憶を完全に外部化するグーグル検索の対極にある、と著者はいう。本と人との関係がそのようなものであり続ける限り、読書という営みがなくなることは決してないだろう。