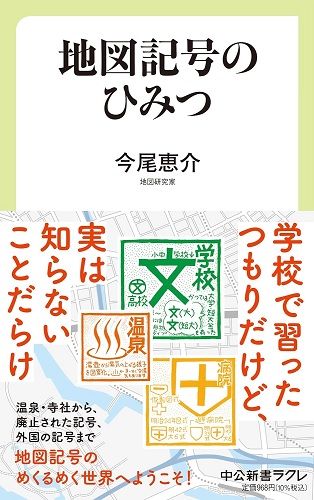等高線の元になったのは
そこで誰かが試みたのが、細い線をびっしり並べて上から見た山や谷を表現しようとする「ケバ」の技法だ。
これなら反対側から見た形も概観はわかる。しかしどのあたりがどう盛り上がり、また窪んでいるかの詳細を再現するには限界がある。その意味で最初に等高線を発明した人の発想はお見事と言うしかない。
ただし、この「水平曲線」の原理を最初に利用したのは「等深線」だったそうだ。考案したのは世界の海を股にかけて商売してきたオランダ人で、海図の中に一定の水深ごとに線を引いたという。
当然ながら水中がよく見えない船にとって、最も避けなければならないのは座礁である。
その恐ろしさは、世界の大動脈スエズ運河で2021年3月に起きた大型コンテナ船の立ち往生で改めて痛感させられた。
等高線はこれを陸上に応用したもので、フランス革命勃発から2年後にあたる1791年にこの国の地形図で初めて用いられ、それから急速に普及した。
※本稿は、『地図記号のひみつ』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。
『地図記号のひみつ』(著:今尾恵介/中央公論新社)
学校で習って、誰もが親しんでいる地図記号。地図記号からは、明治から令和に至る日本社会の変貌が読み取れるのだ。中学生の頃から地形図に親しんできた地図研究家が、地図記号の奥深い世界を紹介する。