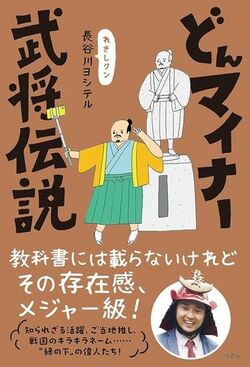天文学と占いを駆使した名采配
浄三さんに関するパーソナル情報ですが、ほとんどが不明です。当時の史料では確認できず、登場するのは後世の軍記物のみになります。
名前についても軍記物によって「白井入道」(『小田原記』など)、「白井入道浄三」(『三好記』)、「白井四郎左衛門入道浄三」(『関八州古戦録』など)、「白井下野(しもつけ)入道胤治(たねはる)」(『千葉伝考記』)というように様々です。
さらに「浄三」の読み方についても不明でして、史料的な価値はないものの、『真書太閤記(しんしょたいこうき)』(江戸時代後期の豊臣秀吉の一代記)にある振り仮名から判断すると、「浄」は当時「じょう」と読んだようですが、「三」にはルビがないので読みは「さん」「ざん」「み」「ぞう」なのかはわかりません。本記事では私の好みで「じょうざん」としています。
浄三さんの経歴について、『関八州古戦録』には「千葉家の一族で、武者修行のために上方に行って、三好日向守長依に仕えたが、この間、下向して当城(臼井城)にいた」とあります。
三好日向守長依とは、おそらく三好長逸(ながやす)のことで、織田信長が政権を握る前の三好政権の有力者だった“三好三人衆”と呼ばれるメンバーのひとりです。
また、浄三さんの能力については「天文の巧者にて、軍配を考え、その利を示す」とあるので、天体や空に関する知識があり、それによって有利な軍勢の配置や進退を考えて助言していたようです。
『三好記』には、旗雲(はたぐも。旗のようにたなびく雲)が出現して多くの人々が吉凶どちらの兆しかが気になっていたある時、浄三さんが「味方の吉事」と占ったと記されています。
さらに『三好記』では「無双の軍配名誉」、『小田原記』では「無双の軍配の名人」と称されるなど、その軍配能力は当時ナンバーワンだったといいます。
ちなみに、1915〜19(大正4〜8)にかけて刊行された『大日本国語辞典』という辞書の「軍配」の項目の中では、代表的な軍配者として、有名な山本勘助(武田信玄の家臣)とともに、浄三さんが紹介されています。