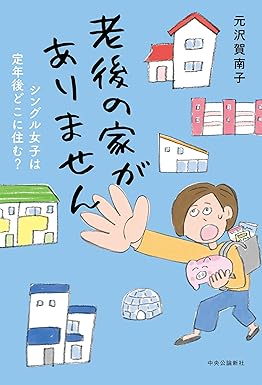やはり、持ち家があるのは大きい
だから、死後に不動産を遺してしまうと、その方が迷惑だと、美佳さんは言います。マンションは全戸の共有物なので、継ぐ人のない物件は、他の区分所有者を困らせるからです。部屋が遺されても、個人の財産なので、他人は処分できません。国が物納を受けても、次の住民が決まらないと、管理費や修繕積立金がストップします。なにより人の住まない空き家は傷みます。
そんな困った“お荷物”を残さないように、伯母を倣って、自分でちゃんとすべての財産を使い切って死ぬのが理想だと、美佳さんは言います。「このマンションは、最後は、売っ払って老人ホームに入る資金にするか、リバースモーゲージで生活資金にするつもり。“負動産”になるようなことはしません」
*****
美佳さんの話を聞いていると、「老後の状況」は、本当に人それぞれだなあと思います。美佳さんはいま、介護離職してしまって、仕事を再開できずに困っています。でも、親と同居しているため、「喰う寝るところに住むところ」には困りません。病気は心配ですが、資金的には、65歳の年金開始まで持ちこたえれば、死ぬまでなんとかなりそうです。
やはり、持ち家があるのは大きいです。家賃のかからない自宅をいずれ相続できるからこそ、日々の生活費だけ用意すれば済みます。もし、美佳さんの実家が賃貸だったなら、と想像すると、ぞっとします。介護のために仕事をストップしたとたん、生活が立ちゆかなくなっていたでしょう。
自分の仕事や収入、公的年金や個人年金がどうなっているか。親の健康状態はどうか。介護が必要か、施設に入れるのか。親の家は持ち家か賃貸か、持ち家として立地は便利な場所かどうか。家以外に、親から受け継ぐ資産はあるか、負債があるか。きょうだいはいるか、いるとして老後にあてに出来るか、逆に面倒を見なくてはいけないか。そうした自分と親きょうだいの関係次第で、状況は千差万別です。同じように大学を出て就職した同世代の人でも、アラ還ともなれば「人生いろいろ」です。老後の生活シミュレーションはそれぞれにすべきだと、つくづく思うモトザワでした。
◾️本連載をまとめた書籍『『老後の家がありません』(著:元沢賀南子/中央公論新社)』が発売中