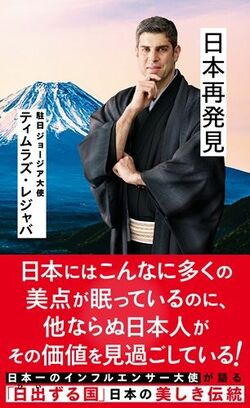就職活動のつらさ
大学2、3年生になると多くの親が子供に対して「就活に向けてちゃんと動いているのか」と圧力をかけ始めます。その親からの圧力がどこから来ているかといえば、社会からの圧力です。
就職していないと世間の目が厳しいから子供にあれこれ言うわけで、「生計を立てられるのか」とか「この子の将来は大丈夫か」という心配よりも先に、周囲の目を気にしているのです。
ジョージアではそんなことはありません。働いていない人も社会に溶け込んでおり、若者の失業者・求職者に対しても「そうなんだ。そのうち、いいところが見つかったらラッキーだね」くらいのスタンスで、あたたかいのです。
このような日本の特徴は、日本人が誰かと知り合うときに「**社の課長の誰々さん」「**大学の教授の誰々さん」という形で、所属とセットになってお互いを認識し、コミュニケーションを取ることにも通じています。
欧米では相手をまず個人として捉え、そのあとで「この人はこういうこともやっている」「こんな仕事もしているんだね」という付き合い方をします。
ところが日本では所属や肩書きがあるのとないのとでは、社会的な地位が天と地ほども違います。だからこそ肩書きがなくならないよう、定年退職した人に天下り先が用意されていたり、顧問職があったりするのかもしれません。
肩書きがなくなった老年男性が急速に衰えるとか、アイデンティティ・クライシスに陥るといった話をよく聞くでしょう。若者についても同様で、学校を卒業しても就職先が得られないと、肩書きのない、何者でもない宙ぶらりんの価値のない存在になってしまう、そう思い込まされています。
そういう社会的な重圧のなかで日本の若者は就職活動を強いられているのです。