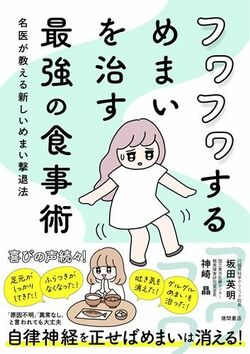体温の「日内変動」が大切
まず、体温について。
私たちの体温は、1日を通してずっと一定なわけではありません。1日のうちで、高くなったり低くなったりと変動しています。これを体温の「日内変動」といいます。
一般的には、体温は朝方から次第に上昇し、午後2時頃に最も高くなり、夜から明け方にかけて下がります。最も高い体温と低い体温を比較すると、約1℃くらいの違いがあります。
この日内変動は、かなりの個人差があり、変動幅が少ない人もいれば、変動幅の大きい人もいます。
これらの体温をコントロールしているのが、自律神経です。
この体温の日内変動を見ていくと、自律神経の状態がどのようになっているのか、それを推測することができます。
当院では、初診の患者さんに対して、「体温記録表」を渡して、毎日の体温の変化を記録してもらっています。
1日のうち、朝食前、昼食後の午後2時もしくは帰宅後、就寝前の3回です。
記録を取ることで、ご自分の体温の日内変動を知ることができます。
当院の中村由美(なかむらゆみ)言語聴覚士がまとめたところによると、体温の日内変動のタイプには、「平坦型」「変動型」「夜間上昇型」の3つがあることがわかっています(下図参照)。

フワフワめまいの患者さんの体温を調べてみると、総じて体温が低い傾向にあります。
ちなみに、基礎代謝(安静にしているときに消費するエネルギーの量)が低い高齢者や、冷え症、低血圧の人も体温が低めです。
体温が1℃下がると、免疫力(体内に病原体が侵入しても発病を抑える力)が30%下がるともいわれています。
自律神経のバランスが乱れ、機能が落ちている結果として、体温の低下(それに伴う免疫力の低下)が起こっている可能性があります。
低体温であることがわかった場合、体温を上げる必要があります。
とはいえ、単純に体温を上げればよいということではありません。
1日のなかで理想的な曲線を描くように、体温を上げる必要があるのです。